令和6年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業報告会が、2025年2月25日(火)に国立新美術館にて開催・配信されました。メディア芸術連携基盤等整備推進事業では、産・学・館(官)の連携・協力により、メディア芸術の分野・領域を横断して一体的に課題解決に取り組むとともに、所蔵情報等の整備及び各研究機関等におけるメディア芸術作品のアーカイブ化を支援しています。また、アーカイブ化した作品・資料等を活用した展示の実施に係る手法等を開発・検討することにより、貴重な作品・資料等の鑑賞機会の創出、インバウンドの増加を図るとともに、アーカイブ及びキュレーションの実践の場として提供することで、今後のメディア芸術の作品等の収集・保存・活用を担う専門人材の育成を図っています。報告会では、本事業の一環として実施した4分野の分野別強化事業の取り組みが報告され、有識者検討委員からの質疑や助言が加えられました。また、事務局調査研究等の報告、「マンガ・アニメ等中間生成物の保存活用事業」の紹介も行われました。本稿では分野別強化事業のうちの「マンガ原画アーカイブセンターの実装と所蔵館連携ネットワークの構築に向けた調査研究」「マンガ刊本アーカイブセンターの実装と所蔵館ネットワークに関する調査研究」を取り上げます。
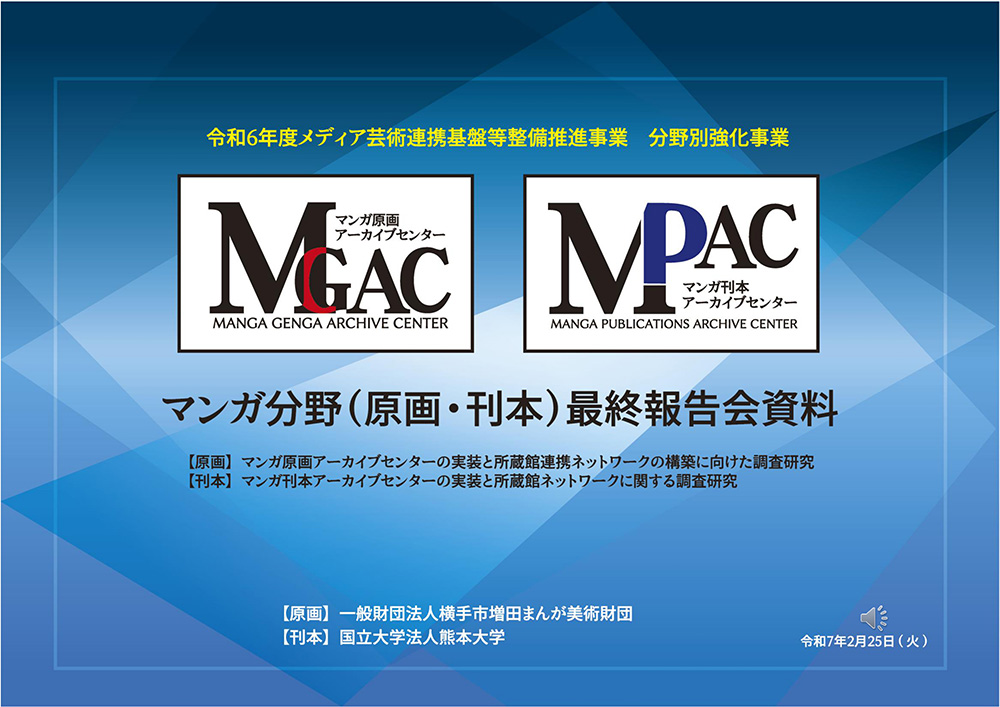
報告者:[原画]一般財団法人横手市増田まんが美術財団 代表理事 大石卓
[刊本]国立大学法人熊本大学大学院 人文社会科学研究部(文学系) 准教授 鈴木寛之
はじめに、マンガ分野における原画部門の事業目的と実施体制について述べる。本事業では、全国の所蔵館や関連施設とのネットワークを強化し、事業のプロセスを可視化・アーカイブするための調査研究を実施している。事業内容については、次の五つの項目に基づき、全国の所蔵館およびマンガ関連施設に関わる人材が集結して事業の推進を図った。
第一に「マンガ原画の保存に関する相談窓口の設置」である。令和2年度よりマンガ原画アーカイブセンター(MGAC)を開設し、マンガ原画に関わる多様な関係者の相談に応じてきた。令和3年度からは原画の一時保管事業にも着手し、これまでに保管した原画総数は47万枚を超える。
第二に「所蔵館ネットワークの構築」である。全国の関連施設とネットワーク会議を開催し、各施設の問題解決に向けた専門家の派遣やアドバイスを実施した。また、一時保管原画を分散収蔵し、新たな連携施設の開拓にも成功した。
第三に「専門人材の育成」である。原画アーカイブの理解を深めることを目的に、有識者による啓発動画を制作・公開し、「マンガ原画保存の手引」も作成した。これらはMGACの公式サイトで公開されている。また、保存・修復の専門機関との共同研究を進め、一時保管原画を教材として提供することで、原画修復技術の向上と後進の育成にも取り組んだ。
第四に「収益および支援体制構築の調査」では、マンガ原画鑑賞のポイントを示す「ゲンガノミカタ展」をパッケージ化し、会場規模に応じた巡回展示を行った。加えて、作家の展覧会に鑑賞ポイントのテキストを提供し、解説冊子の製作・販売を通じて保存意識の向上にも努めた。
第五に「アーカイブ協議会の開催」である。令和6年度には「原画」および「刊本」事業の合同会議を計11回開催し、共通課題の抽出や対策の検討、合流後の体制構築、継続運営の中長期計画を協議した。なお、次年度以降の事業内容と体制については、後半にて報告する。
続いて、成果と課題について述べる。5年間の事業実施を通じ、相談窓口の開設や47万枚以上の原画の一時保管、新たな協力施設の参画など一定の成果を上げたが、課題も多く残る。事業の核となる窓口体制と広報の強化、保管スペースの確保、所蔵館ネットワークの拡充、新規協力施設・団体の開拓、一時保管原画の利活用促進と収益改善策の構築などが求められている。これまでに築いた連携と実績を基盤に、引き続き課題に取り組んでいく。
次に、マンガ刊本アーカイブ事業について、過去5年間の活動実績と課題、今後の展望を三つのテーマに分けて報告する。
第一に「マンガ刊本アーカイブセンター(MPAC)の設置」である。令和5年12月に熊本大学にMPACを開設し、出版されたすべてのマンガ刊本を少なくとも一冊ずつ保存することを目的としている。刊本にまつわる相談窓口を運営しており、これまでの相談受付件数は14件で、すべてが利活用に関するものであった。これにより刊本ネットワーク内の連携が強化された。
課題としては、①これまで「モノ自体は集めず、相談窓口に徹する」という方針を採ってきたが、今後は実物の収集の必要性を再検討する。②保存すべき刊本資料の優先度や範囲の確定。③刊本の利活用に関する需要の見込み。④全国の連携機関や出版社、個人コレクターなどに刊本アーカイブの意義のさらなる発信が求められる。また、刊本自体がもつ博物資料としての価値を広める必要がある。なお、MPACの相談案件としては、海外や個人からの寄贈依頼、重複資料の展示会等への資料の貸与依頼などが挙げられる。
第二に「刊本ネットワーク協同所蔵リストの構築準備」である。連携館同士が刊本の所蔵情報を共有することを目的とし、将来的に原画情報やメディア芸術データベース(MADB)との情報連携を行う体制の構築を目指している。現在、MADBとの連携を前提にメタデータ(分類・書誌管理項目)のすりあわせについて、所蔵館3館(北九州市漫画ミュージアム・明治大学米沢嘉博記念図書館・京都国際マンガミュージアム)の単行本データをサンプルに協同所蔵リストの項目を検討し、そのイメージを共有した。今後は、原画と刊本が一体化した際にデジタルデータをどのようにアーカイブするかが検討課題となる。
第三に「熊本における刊本プール・分散収蔵・資料利活用実験」である。実績として、これまでに刊本整理の知見の集約、雑誌資料・海外資料の整理分類の知見集約を進めてきた。また、5年間の刊本プールの作業実験として、分散収蔵を試み、自治体の協力のもと譲渡会や閲覧の機会を設けるとともに、学校図書館との連携で複本の利活用を行ってきた。MPACの最重要課題は「最低限一冊」の保存だが、ブロック制などによる全国的な複数保存と利活用の方策も検討している。リスク分散の観点からも有益である。
課題としては、ボランティアベース作業からの転換、資料の長期保存のためのポリシー等の策定が求められる。
年間を通じて開催されたアーカイブ協議会において議論した、次年度以降の事業体制および事業内容の構想を報告する。
まず、事業体制については、次年度から原画事業と刊本事業を統合し、MGACおよびMPACの窓口業務を一本化することが望ましいとの結論に至った。また、これまで横手市増田まんが美術財団および熊本大学が受託していた事業を、マンガ分野アーカイブの産学官連携を基調として設立された「一般社団法人マンガアーカイブ機構(MAC)」が引き継ぐことが適切であることが確認された。さらに、全国を三つのブロックに分け、それぞれに中核施設を設置することで、円滑な事業推進体制を構築し、全国的なネットワークの発展につなげる考えである。
一方で、事業内容については、両事業の窓口業務の一本化により相談内容の情報集約と対応策の総合的判断を可能とする体制を整備する。ブロック体制の構築支援では、現行のアーカイブ体制の強化に加え、北海道や沖縄といった重要エリアへの拠点形成を進める。資料の一時保管については、両事業のこれまでの成果とノウハウを継承しつつ、資料の収集および整理の基準を明確化し、適切な資料保管を目指す。また、共通の資料収集基準として「刊本リスト(仮称)」を早期に構築し、MADBとの連携を視野に入れながら進める。加えて、両事業が融合した新たな展覧会パッケージの開発を通じ、収益面の強化にも努める。
補足として、それぞれの業務に専従スタッフを配置するとともに、適切な予算が措置されることで、継続的な事業推進が可能な体制構築を目指す。さらに、ブロック体制のあり方についても検討を重ね、各団体や施設が自身の状況に応じた参加基準を選択できるよう、5段階の基準を設け、基準ごとの作業区分も明確化する。そして、各基準に応じた権利やメリットを提示し、より多くの関係者が参加しやすい環境を整備する。
最後に、要望および展望について述べる。これまでの5カ年事業により一定の研究成果は得られたものの、膨大で喫緊の対応が求められる資料群のアーカイブに対しては、スペース・人材・予算の確保が不可欠である。今後は、調査研究事業からアーカイブの実務遂行事業へと移行するフェーズでもある。短期的な資料保護にとどまらず、中長期計画の立案と実施を通じて、「メディア芸術ナショナルセンター(仮称)」や将来的なアーカイブ体制の強化に寄与することを目指し、事業の拡大と充実に努めていきたい。

[原画]実施報告書(PDF)
[刊本]実施報告書(PDF)
※URLは2025年9月24日にリンクを確認済み