葛西 祝
ビデオゲームは、開発サイドは「こんなふうに遊んでほしい」と方向性を定めてつくるもの。対してプレイヤーは、与えられたゲームに対してどういうふうに攻略するか手練手管尽くすものといえます。ですが、プレイヤー側のゲームプレイも、もし開発側が想定している内容へ近づくような仕組みが入っていたらどう感じるのでしょうか。現在、「メタAI」と呼ばれる技術によりそのようなことが実現可能になりつつあります。それらはもちろんプレイヤーを楽しませるためですが、プレイヤー側からすれば、自分の意思で遊んでいると思ったものが違っていたとしたらどう思うのでしょうか。その是非を、『ビデオゲームの美学』(慶應義塾大学出版会、2018年)を上梓するなど、ゲーム研究と美学を専門とする松永伸司氏と、現役の研究・開発者としてスクウェア・エニックスのAI部でメタAIの研究に取り組む水野勇太氏が議論しました。

――メタAIに関する松永さんと水野さんの議論って、実は僕も6年ぐらい前から続けているのを見ているんですよね。そもそもなぜ議論するようになったのでしょうか。
水野 2017年に開催した『ハーフリアル』の読書会1で、僕がメタAIの研究開発をしていると説明したとき、松永さんが「違和感がありますね」みたいな反応をしたのが最初だと思います。
松永 「プレイヤーは常にメタAIの裏をかくことをやり始めるんじゃないか、それについてどう考えているか」という質問を最初にした記憶はあります。
水野 たしか僕は「むしろ望むところだ」と返した覚えがあります。プレイヤーがメタAIに対して遊ぶ状態はある意味、開発者側としては理想的だというお話をしたと思いますね。
――改めて、メタAIとは何かを教えてもらってもいいですか。
水野 メタAIとはゲームの環境や世界をシミュレーションし、全部を包括してコントロールするAIです。ウィル・ライトが2005年に行った講演「AIデザインパースペクティブ」が一番初めに言及されたものであるようです。
この技術は難易度調整から始まったといわれています。古くは『パックマン』(1980年)がプレイヤーのゲームの腕前をプログラムで判断し、難度を調整していく「セルフゲームコントロールシステム」と呼ばれる仕組みを提示しました2。
また『ゼビウス』(1982年)も近いものがありました。プレイヤーがやられたときそのテーブルが巻き戻って、弱い敵から出直す仕組みがあります。これは失敗したプレイヤーがまた同じ強さの敵と戦う必要がないように難度を調整しています3。

――難易度調整とはプレイヤーに適切に遊びやすくする意図が大きいんでしょうか?
水野 メタAIは難易度調整以外でも、ゲーム全体をコントロールし、体験の波をつくることが目的です。
例えば対戦ゲームにおいて、負けているチームに特殊ゲージが溜まりやすくなるようにして対戦バランスを調整します。またプレイヤーがあるキャラクターを死亡させてしまったときにほかのキャラクターをあてがうなど、ゲームの世界のリアリティを高めるためにゲーム世界で起こったことが破綻しないようにするものも含まれます。
音楽をコントロールすることだったり、ゲームの進行自体をコントロールすることだったり、いろんなものをコントロールすることが含まれています4。
――現在のゲーム開発でなぜメタAIが必要なのかもついでにうかがえますか。
水野 AAAタイトルはやはり開発費がとてもかかります。より多くの人に購入していただき、満足してもらうことを考えたとき、人それぞれの状態に合わせる必要があります。
これまでのゲームのつくり方は、ゲームデザイナーが設定した一番良いバランスの決まったものをつくるのが基本でした。ただその場合、想定より上手い人には「簡単すぎるな」と受け取られたり、バトルが苦手な人にもバトルを要求したりしてしまいます。
なのでいろんな人が満足するように、その人に合った体験を提供するメタAIを導入するわけです。プレイヤーの行動をメタAIがセンシングし、ゲームの状態を変えることが必要だと思ってますね。
それを僕は「おもてなし」と考えています。
――そんなメタAIですが、松永さんが「違和感がある」という感覚はどういうところから発生していますか。
松永 僕が違和感を覚える一番のポイントは、「ゲームをプレイする楽しみと、おもてなしされることは本質的には相反するんじゃないか」ということです。
――詳しくご説明をお願いできますか。
松永 ゲームの魅力の一つに、挑戦課題を乗り越えることがあると思うんです。
メタAIの問題は、要するに自分の能力に合った形で課題が設定されるっていうことですね。リアルタイムでプレイヤーの能力がチェックされ、「この人の能力は大体こんなもんだろう」と判断し、それに適した課題が与えられるという。プレイヤーが適度に心地よくなれるように調整するものですよね。
――基本的には開発側が目指したいことだけど、プレイヤーとしてはおせっかいに思えることもあるということでしょうか。
松永 もっというと、そもそもすべてのおもてなしが違和感ありませんか。例えば旅館に泊まったとき、勝手に布団を敷かれているなど、なぜこちらの行動を先回りして推測しているのか。
――お話を戻しますと、メタAIがおもてなしする範囲についていかがでしょうか。
水野 そもそもゲームに関しては2種類あるんじゃないかっていうふうに考えています。
一つは、まさに松永さんが挙げた挑戦的に遊ぶタイプのゲーム。いわゆる高難度のアクションゲームであったりとか、シューティングゲームで面クリアを目指したりするものですね。
もう一つは娯楽的に遊ぶゲームがあると思っています。サイコロの出た目でランダムにマップを移動していって、どっちが先に着くかを楽しんだり発生するイベントを楽しんだりする、勝ち負けよりその体験自体を楽しむゲームです。
――補足すると、娯楽タイプは勝ち負けより物語や世界観を楽しむことを目的とするゲームですよね。
水野 挑戦タイプのゲームをおもてなしで調整してしまうと、たしかに「どこまで自分自身でできたことなのか?」と揺らぐ。どうバランスを取るかは僕もまだ研究中なので難しいんですね。
だけど娯楽タイプに関しては、むしろどんどんおもてなしして一番いい状態にしてもらったほうがいいんじゃないかと思ってますね。
松永 最近のゲームタイトルだと、メタAIを使ってることはプレイヤーにオープンにされているんでしょうか? あるいは、メタAIを使っているかをプレイヤーに知らせるべきか否かについて、どうお考えですか。
――確かに「このゲームではメタAIがゲームプレイの調整をしている」という情報をプレイヤーが知っているかどうかで意味が違ってきます。
水野 難しい質問ですね……。先ほどの話に戻しますと、娯楽タイプのゲームにおいてはメタAIが入っていることは積極的にオープンにしてよいだろうと思っています。
ただ、挑戦タイプにこっそりメタAIを入れるのは基本的には難しいし、いろいろ考えると良くないだろうなと思っています。
というのは、結局さっき松永さんがおっしゃったとおり、「自分がうまくなったと思っていたら実はメタAIが調整していてくれた」というのはやっぱりゲームのプレイヤーを騙す形になるからです。
なので「娯楽的に遊んでください」って形でメタAIが入っていることをオープンにして遊んでもらうことは成立するのかな、という感じですかね。
松永 そうすると、娯楽タイプのゲームでオープンにしないことはありうるということですか。
水野 つくり手としては公開するかしないかだけです。その上でメタAIの存在がバレたみたいなことはありうると思います。
挑戦タイプが好きなプレイヤーはメタAIの存在がオープンにされてなかったら絶対に怒ると思います。そこは伏せないほうがいいというのはわかるんですけど、娯楽タイプが好きなプレイヤーがどういう反応を返すかは僕もちょっと予想できないです。
――反応が分かれそうですね。挑戦タイプのように競技性が強い場合、メタAIが関わると「そのゲームは平等といえるのか?」という疑問があります。
水野 やはりメタAIがどういうバランスで、どの部分に入っているかが大事だとは思っています。
例えばサイコロを振って遊ぶ娯楽タイプをプレイするとします。そこで勝った負けたを純粋な結果だと思っていたのに、実はメタAIがサイコロの出目を全部コントロールしていたのはよろしくないと思うんです。
松永 挑戦タイプと娯楽タイプ、そこにメタAIがオープンにされているものとされてないものの、組み合わせで4パターンあることになると思いますが、実例としてはどうなっているのでしょうか。
水野 ちゃんと分類したことがなかったんですけど、僕の知る範囲ではゲームごとに違ってるものがあります。「ゲームバランスを操作するAIがある」と公言しているものもあれば、言わないものもあります。
松永 先に水野さんがおっしゃった『ゼビウス』的な難易度調整も、存在を特に明言してないケースが多いんでしょうか。
水野 難易度調整の仕様は公式ではプッシュしていないけれど、のちのち「そういった技術が入っている」と明らかになって、今はオープンになっている形が多いと思います。
少なくともオープンになっている事例を振り返ると、例えば『ゼビウス』は挑戦タイプのシューティングゲームといえます。
けれど「一度やられると弱い敵のところに戻る」仕様も、そこを売りにして「それもゲームの楽しみ方なのでそれを踏まえて楽しんでください」形ではないとは思います。つまり、挑戦タイプ、クローズ型ですね。
――メタAI的な機能という意味では『バイオハザード4』(2005年)5や『天外魔境Ⅱ』(1992年)6の動的な難易度調整も宣伝段階で公言されていませんでした。
水野 必ずしもメタAIの存在を伏せる理由が「プレイヤーに知られると良くないから」ではない事例があるっていうことがメタAIにとっては非常に大事だと思いますね。
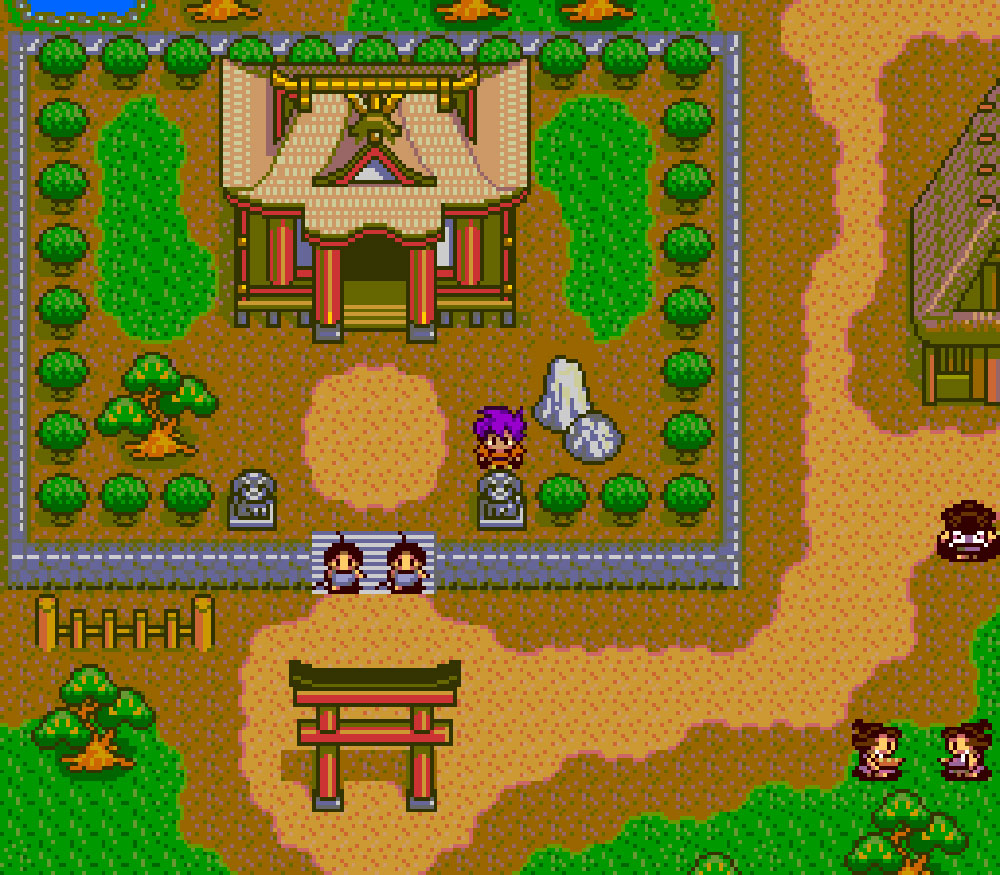
――ただ製品としてのビデオゲームを考えると「開発側はすべての面でおもてなしするのが普通で、メタAIもその一貫ではないか」とも思います。
松永 確かに。メタAIというよりゲームデザイン全般に関しても、開発者はおもてなしの気持ちがあるのかどうかを聞きたいです。
水野 なるほど。結論からいうとあると思います。いわゆるレベルデザインも「プレイヤーをどう楽しませるか」を踏まえてマップの配置をしますよね。
なので必ず何かしら楽しませたいとか、おもてなししたい思いで調整されています。どのゲームにおいてもそういう思いは入っていると言っていいと思いますね。
――ゲームには大なり小なりのおもてなしが存在してますが、松永さんはどこからおもてなしに違和感を覚えるラインがありますか。
松永 難易度のバランスがいい感じに設定されてるとか、楽しめるようにデザインされてるというだけならいいのかもしれませんね。そうすると、メタAIの違和感はむしろ、プレイ中に動的にセンシングされてプレイヤー個別のチューニングをしてくるというところにあるのかもしれない。
――プレイヤーの事情を察してくることに違和感があるのでしょうか。
松永 「自分がどこまで自分のことをオープンにしているか」についての自覚とのあいだにギャップがあるという問題なのかもしれないですね。自分がオープンにしてないはずのプライベートな部分を勝手にセンシングされて、何かをレコメンドされることに対する抵抗感なのかもしれません。
さっきの話に戻りますが、「プレイヤーにメタAIの情報をどこまで公開するか」は、ある程度倫理的な問題だと思うんです。つまり、サービスの裏である種のメカニズムが働いていてユーザーの情報を取得していることをユーザーに伏せるということには、たとえユーザーのためになるとはいっても、何か倫理的な悪さがあるのではないかということです。
水野 おそらく今後メタAIで自動的に判断し、プレイヤーごとに反応を変えるサービスがたくさん出てきたとき、「裏でそういうメカニズムがありますよ」とあらかじめ明示する必要が出てくるのではと思うんですね
――いずれにしてもメタAIがプレイヤーを騙すようになってしまうのは一つ懸念としてあったと。
水野 そこの境界線っておもしろい話だなと思っていて、一番わかりやすいのはメタAIであるかどうかに関わらず、対戦ゲームで真剣に対戦しているつもりだったのに、相手は勝たせようと思って実は手を抜いたみたいなことですよね。
それはやっぱり欺いていることになっているのでよくないということです。なので調整をしたのですが、それを隠していることが後から明らかになるのは悪いことです。
逆に調整がないことを期待しないシチュエーションでは、調整されていることってどこまで悪いのかなっていうところはあります。
――難易度の調整というよりも、物語とか世界観を体験するタイプのゲームでメタAIを使うことはあるのでしょうか。
松永 例えばオープンワールドゲームにおけるイベントの発生については、調整なしだと毎回同じようなパターンになったりしますよね。
一つひとつ設定するのは大変なので、メタAIが「ここのところイベントが発生していないから、そろそろイベント発生させましょう」とイベントを発生させる、みたいな使い方はありえそうに思えます。
水野 後から「実はそういう調整が入っていた」と明らかにされた場合、プレイヤーはどれぐらいの嫌悪感を感じるかはわからないですね。
松永 さっきの違和感とはまたちょっと別ですが、自分のプレイでだけ起きた「偶然の出来事」で、「自分だけの物語」だと思っていたものが、実は仕組まれていましたとなると騙されたと感じそうな気はしますけれども。
水野 なるほど。偶然を装った何かといわれれば。確かにそうかもしれない。本当に私だけがたまたま出会った体験だっていうふうに期待してしまう。
松永 その期待が裏切られるっていうことになりそうです。偶然性というか「一回きりの出会い」みたいな体験の味わいが評価される場面だと、欺瞞になりそうな気もします。
水野 確かにそれはありますね。ただ微妙に話がずれています。僕が想定していたのは、イベントが期待している頻度で起こらず、ゲームが退屈になってしまう問題です。そこでメタAIによって適切な頻度でイベントを起こしましょうっていう解決を想定しました。
松永さんが言っているのは、そこでも偶然性を見出すというか、物語性を期待するみたいなことですよね。
松永 そうですね。
水野 そこはメタAIにおいて大事なポイントかなと。イベントが起こらない問題を解決するため、こういうメタAIをつくりましたというときに、そこにプレイヤーが物語性を見いだすことまで想定して問題ないか考えないといけないというのは大変興味深い指摘です。
なので簡単な解決として、「メタAIが入っています」と事前にお伝えしておくことなんですけども。そうすると倫理的にはセーフになるんじゃないでしょうか。
松永 でもメタAIが関わっているのがわかると、本物の偶然性とは思えなくなってしまうんじゃないでしょうか。本当にデザインされていない良い感じの出来事、これは「奇跡」と言ってもいいと思うのですが、それに遭遇するという独特の経験が毀損されるんじゃないかということです。
メタAI使ってますと言われたら「いい感じのこのイベントもメタAIの仕業なんですか?」と疑ってしまう。逆にいえば、メタAIが入っていない場合なら起こるとされているゲーム上の「偶然性」がそもそも何によって成り立っているのかを、あるいは本当にそれは「偶然」なのかを、ちゃんと考えないといけないのかなと思います。ゲームは純粋な自然ではなく、多かれ少なかれデザインされているもののはずなので。
僕の好きなエピソードで、『GTA IV』でNPCとドライブデートしてたら事故でそのキャラが死亡する体験をしたプレイヤーの話があるんです7。
プレイヤーの独白によると、イベントで設定された死じゃなくて「偶然」なんですね。つまり誰もデザインしていない悲劇的なドラマを、その人自身が「たまたま」体験したという話です。こういうプレイ経験がメタAIの時代でも同じように起きうるのか?が疑問ですね。
水野 メタAIの関わり方は100か0かではないので、ある範囲だけコントロールすることもできます。もし今のNPCの偶然の事故を、メタAIが100%コントロールして仕組んだとなると、それは嫌ですよね。
NPCが事故に合いやすいタイミングの調整とか、一緒に車に乗ったときに目的地に着くまではメタAIがコントロールしてるけど、そのあと事故になるかどうかはプレイヤーの操作や判断に委ねられる形にも、もちろんできます。
ただ100%がダメなら80%ならよいか、30%ならよいか、どこが一番良いバランスかを自動的に調整するのは、正直まだメタAIではできていないです。そういうセレンディピティが残る余地を常に残すメタAIをつくることが重要って未来はありうるかもしれないとは、今お話を聞いていて思いましたね。
――人の手でデザインされたゲームに対し、偶然性をどこまで求めるかもあるのでは。
松永 水野さんとメタAIの話をするときに毎回言ってる気がしますが、個人的な気持ちとしては、ゲームは自然であってほしいんですよ。山みたいな。
山って別に人間のことを一切気にしてないじゃないですか。登山者をチラチラ見て、登りやすいように「ここにいい感じの崖をつくろう」みたいに出来てない。それがいいんです。
水野 なるほど。人間をチラチラ見てデザインすることが一切ないのが自然だと思うんですね。
松永 なぜかゲームもそれに近い感覚でやってるところがあります。ゲームは人にデザインされたものであるはずなのに。
――そこは普遍的な考えなのか、松永さんのこだわりなのかは気になります。
松永 最初の話に戻りますけど、プレイヤーっていうのは意図された遊び方を承知のうえで、常にあえてそこから外れるなど、自分なりの楽しみを見出す遊び方をするものだと思います。
ゲームデザイナーが想定してる遊び方はわかったうえで別の、自分なりの楽しみを見出すのは普通にみんなやってあることだと思います。それがまさに、ゲームを自然として見るということなのかもしれません。
ゲームを「デザインされた人工物」というよりも「そこにあるだけの物」として捉えると言い換えてもいいかもしれません。RTAなんて開発者の意図せざる遊び方という点で典型的じゃないですか。
これは水野さんに聞いてみたいのですが、メタAIってつくり手がゲームプレイをすべて支配したいという発想の現れのように見えるんですね。つまり神になりたい感じに見える。開発者の意図にあえて反抗する天邪鬼なプレイヤーすらも支配してしまうような神というか。その発想と、ゲームを自然として見たいという発想とが対立しているような気がします。
水野 基本的に僕はゲームデザイナーが考えたゲームが最高であるべきだと思っています。デザイナーが考えた以外の遊び方のほうがおもしろいということは、ゲームデザイナーの敗北なんです。
ゲームデザイン至上主義の観点では、メタAIはゲームのなかにゲームデザイナーを置くことを目指しているといえます。その意味ではメタAIが提供するゲームが一番おもしろいゲームになるべき。
あるいはデザイナーが想定したデザインから外れる遊び方もメタAIがフォローするべきという、究極的にはそこもカバーしたい野望を持っているほうが良いのではないかと。
――やはり開発側はプレイヤーの体験を制御していきたいものですか。
水野 松永さんは「ゲームは自然であってほしい」とお話しされていますが、そこには挑戦的なゲームプレイを常に要求しているのではないかとは感じています。
自然であるゲームというのは眺めるとか存在自体を美しいみたいな話をしているのではなく、自然たるゲームに対して自分が立ち向かうということが楽しいっていう話をされているんですよね?
松永 挑戦が典型的ですが、もうちょっと一般化すると自己変容ですかね。
――自己変容とは、どういうことを指していますか。
松永 自分が変わるきっかけになるという点にこそ、ゲームをプレイすることの重要な価値があるのかなと思っています。自分にチューニングされるゲームだと、基本的に自分は変わらなくて済む。むしろ、現状の自分を慰めてくれるものだと思うんです。
受け手にチューニングされた娯楽っていうのは、基本的に「あなたはそのままでいいよ、そのままで快適だよ」と言ってくれるようなものですよね。そういう価値観にはちょっと抵抗があります。
これはかなり個人的なゲーム観でもあるし、芸術観でもあるんですが、たぶん僕自身がゲームにそういう自己変容のきっかけを求めてるんだと思います。
脚注
水野 勇太(みずの・ゆうた)
1982年、兵庫県生まれ。大学卒業後、大手ゲーム会社で、ステルスアクションゲームの敵AIプログラマとして、ゲーム業界のキャリアをスタート。その後、企画職へ転身。スマートフォン向けタイトルのプランナー、ディレクターとして、ゲームデザインとディレクションの経験を積む。
現在は株式会社スクウェア・エニックスにて、AIテクニカルゲームデザイナーとして、エンジニアとディレクターという二つの経験を活かして、進歩した「メタAI」実現のための研究に取り組むとともに、さまざまなAI技術を実際のゲームに適用/ゲーム開発フローに導入するためのプロジェクトマネージャーとしても業務に取り組んでいる。
松永 伸司(まつなが・しんじ)
美学者。京都大学文学部メディア文化学専修准教授、立命館大学ゲーム研究センター客員研究員。専門はゲーム研究と美学。著書に『ビデオゲームの美学』(慶應義塾大学出版会、2018年)、訳書にイェスパー・ユール『ハーフリアル』(ニューゲームズオーダー、2016年)、ネルソン・グッドマン『芸術の言語』(慶應義塾大学出版会、2017年)、ミゲル・シカール『プレイ・マターズ』(フィルムアート社、2019年)など。2015年度より、文化庁メディア芸術連携促進事業内の研究マッピング(ゲーム分野)事業の調査担当。
※インタビュー日:2023年3月15日
※URLは2024年3月15日にリンクを確認済み