中垣 恒太郎
英語圏で医療現場に取り入れられている「グラフィック・メディスン」と、日本の「医療マンガ」について論じる本連載。なかでもグラフィック・メディスンは近年、研究書などが積極的に刊行され、学問分野としての定着を見せています。最終回となる今回は、領域を横断して行われている海外の研究や、日本の医療者教育における取り組みなどを紹介。「個」の物語に光を当てる「ライフライティング」に注目しながら、「グラフィック・メディスン」の特徴と可能性を考察します。
連載目次

2022年7月14日から16日に、国際グラフィック・メディスン学会がシカゴ大学にて開催された。2019年度にイギリスのブライトンで開催されて以降、久しぶりの対面での開催となるもので、大会テーマは「絆をつなぎ直す」というものであった。
日本語での翻訳版もある『母のがん』(高木萌訳、ちとせプレス、2018年)の著者、ブライアン・フィースによる講演や、永田カビ『さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ』(英語版の刊行は2017年)を博士論文の題材の一作品として準備しているイギリスの大学院生の報告など。学会のクロージングセッションでは2022年から新たに創設された「グラフィック・メディスン賞」の発表があり、フランスの女性アーティスト、エロディ・デュランによる『パレンセシス(Parenthesis)』(Top Shelf Productions、2021年)が選出された。20代半ばに脳腫瘍の症状が現れて以降の半生を描く回想録である。オリジナルとなるフランス語版は2010年に発表されたものであり、英語版が刊行されたタイミングでの注目となっているが、非英語圏の作家による作品が第1回の受賞作となったことからも国際性が主要な観点となっている。日本の医療マンガ作品の英語訳は現在までのところ多くはないのだが、国際的な広がりを求める機運が高まっているなかで英語版による発信にも期待したい。2023年の学会は7月中旬にカナダのトロントでの開催が予定されている。
グラフィック・メディスンにまつわる研究書も増えてきており、学問分野としての定着を実感させる。ハワイ大学出版局による叢書より刊行された論集『グラフィック・メディスン(Graphic Medicine)』(2022年)は、ハワイ大学マノア校を拠点に1978年から刊行されている学際的な学術誌『バイオグラフィ』の記念特集号(第44巻2・3号)である。『バイオグラフィ』は文学、歴史、芸術、社会科学を横断して「ライフライティング」(人生をめぐる記述)を学際的に捉えようと試みる学術誌であるが、「ライフライティング」という観点とグラフィック・メディスンとの相性は確かに似つかわしい1。グラフィック・メディスンの創設メンバーの一人であり、『グラフィック・メディスン・マニフェスト』でも中核を担っているスーザン・M・スクワイアーほか、寄稿者の背景も多彩であり、英米のみならず、カナダ、オーストラリア、オランダ、ドイツ、分野も比較文学、視覚文化研究、アーティストなど多岐にわたる。障害、認知症、精神疾患を描いたグラフィック・ノベル作品の分析が中心となっている。
さらに、人文科学、社会科学を扱うイギリスの大手学術出版社、ラウトレッジ社が近年、グラフィック・メディスンにまつわる研究書を積極的に刊行している。ラウトレッジ社の研究書3冊、『グラフィック・メディスンにおける精神病のメタファー(Metaphors of Mental Illness in Graphic Medicine)』(2021年)『ジェンダー、摂食障害とグラフィック・メディスン(Gender, Eating Disorders, and Graphic Medicine)』(2021年)、『不妊を描いたコミックスとグラフィック・メディスン(Infertility Comics and Graphic Medicine)』(2022年)はいずれも著者2名による共著であるが、3冊とも南インドの研究者、サティヤラージ・ヴェンカテーザン教授(ナショナル・インスティテュート・オブ・テクノロジー、ティルチラーパッリ校人文社会学部)が中心著者となっている。アメリカ文学の批評理論から出発し、「健康人文学」(ヘルス・ヒューマニティーズ)を専門領域として掲げ、グラフィック・メディスン研究を推進している2。「精神病」「ジェンダーと摂食障害」「不妊」を扱った英語圏のグラフィック・メディスン作品を題材に、「ライフライティング」、医療者教育、表現することによるセラピー効果とコミュニティ構築の観点などを通して、ヘルスケアの領域を人文学の枠組みで捉えようと試みている点に特色がある。なかでも、ヴェンカテーザン教授が「健康人文学」の概念を踏まえていることからも、「医療人文学」(メディカル・ヒューマニティーズ)を「健康人文学」として捉え直すことによって、医療の専門化からこぼれ落ちかねない側面までも包括的に扱おうとする姿勢が強調されている。
あるいは、奥山佳子教授(ハワイ大学ヒロ校)による日本のマンガにおける障害表象研究として、『マンガにおける障害の再フレーム化(Reframing Disability in Manga)』(University of Hawai’I Press、2021年)、『当事者マンガ――脳およびメンタル・ヘルスにまつわる日本のグラフィック・メモワール(Tōjisha Manga: Japan’s Graphic Memoirs of Brain and Mental Health)』(Palgrave、2022年)などもある。グラフィック・メディスンの概念を直接踏まえているわけではないのだが、コミュニケーション研究のなかでも、「ろう者学(聴覚障害研究)」および手話によるコミュニケーションを主たる専門領域とする著者により、聴覚障害、視覚障害、車椅子利用者、自閉症、性同一性障害(性別違和)、アスペルガー症候群などを描いた日本のマンガが紹介されている。山本おさむ『どんぐりの家』(1993〜1997年、『ビッグコミック』連載)、軽部潤子『君の手がささやいている』(1992〜1996年、『mimi』連載)、吉本浩二『淋しいのはアンタだけじゃない』(2016〜2017年、『ビッグコミックスペリオール』連載)、井上雄彦『リアル』(1999年〜、『週刊ヤングジャンプ』連載)、有賀リエ『パーフェクトワールド』(2014〜2021年、『Kiss』連載)、さそうあきら『花に問ひたまへ』(2014〜2015年、『WEBコミックアクション』連載)、波間信子『ハッピー!』(1995〜2010年、『Be・Love』連載)、逢坂みえこ『プロチチ』(2011〜2014年、『イブニング』連載)、戸部けいこ『光とともに…~自閉症児を抱えて~』(2001〜2010年、『フォアミセス』連載)、文:山口かこ、絵:にしかわたく『母親やめてもいいですか――娘が発達障害と診断されて…』(かもがわ出版、2013年)、平沢ゆうな『僕が私になるために』(2016年、『週刊モーニング』連載)、志村貴子『放浪息子』(2002〜2013年、『コミックビーム』連載)など、日本のマンガ文化の豊かな発展を英語圏の文脈に位置付ける資料性の高いもので、これから各々の作品が英語翻訳され、海外の読者にも広く届くための後押しとなることも期待される。
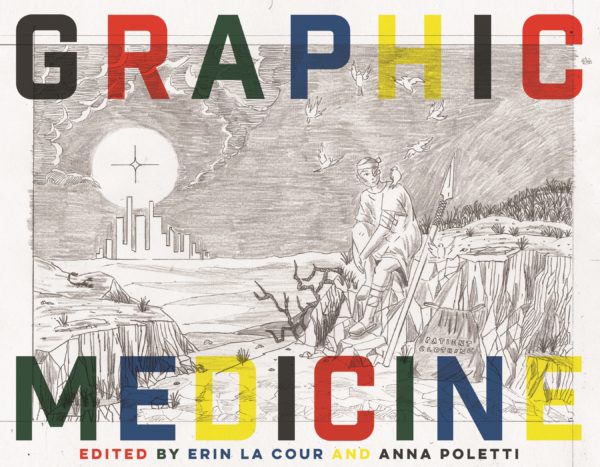
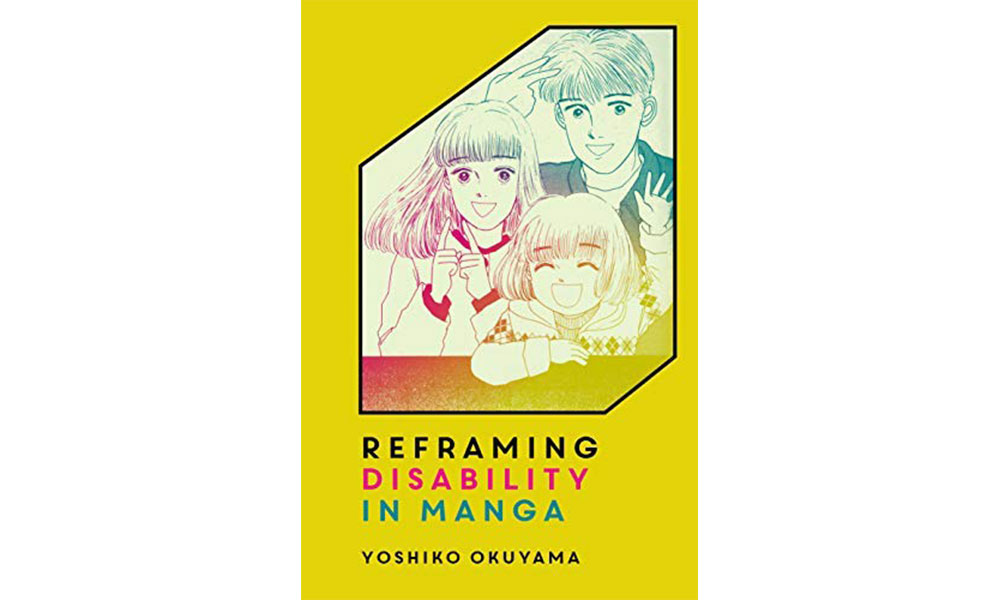
日本の医療者教育においても、マンガを活用した取り組みが進展を示している。『漫画なら64』(編者:高橋優三、著者:内藤知佐子、岡本華枝、宮田靖志、藤野ユリ子、NextPublishing Authors Press、2022年)は、「医療人を育てるには、非言語メッセージによって学習者に考えさせるタイプの教材が求められる」(「巻頭言」)という理念に根差した、マンガを導入した医療者教育向け教材である。第53回医学教育学会(2021年)によるワークショップ「漫画を使った医療プロフェッショナリズム教育」を踏まえた成果であるようで、医療者教育に携わる医学・看護学系教員による原作に基づき、特定のシチュエーションが1ページのマンガで「状況」として提示され(合計64例)、その状況に対するディスカッションの論点が「課題」として付されている。医療にまつわる日本のマンガ文化は確かに多岐にわたっているけれども、エンターテインメントとしての性質上、感動を煽る演出などが必然的に入り込んでしまうものだ。国際的なグラフィック・メディスンの観点からも、『漫画なら64』は興味深い実践例を示している。
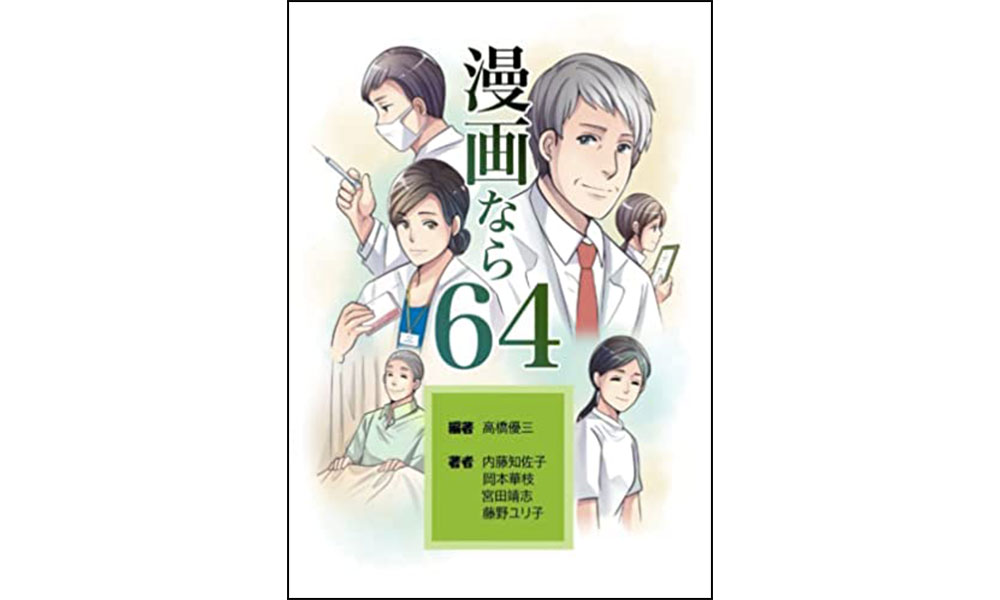
日本グラフィック・メディスン協会では「グラフィック・メディスン30選」として選定された作品を中心に扱う勉強会を2022年に計7回開催した。「アルツハイマー」「がん」「高齢者・介護」「ダウン症の告知と受容」「更年期の表現」「摂食障害」「発達障害」など毎回テーマを設定し、英語圏のグラフィック・メディスン学会が選定した「30選」の作品を取り上げ、その特徴を具体的に紹介しながら、日本のマンガ作品を比較参照しつつ、日本においてどのように応用可能であるかを探ることを目指した3。
「グラフィック・メディスン30選」に選ばれている作品は主として「グラフィック・メモワール」と呼ばれるもので、日本では闘病エッセイマンガに相当するものだ4。グラフィック・メディスンの概念が提唱される過程においても、「グラフィック・パソグラフィ」(病跡学)として、それぞれの疾病が心情とあわせてどのようにヴィジュアル表現で記録されているかを分析する点にとりわけ注目がなされていた。
また、「30選」のラインナップには、さまざまな障害や、子どもの死をめぐる心のケアを描いた作品も取り上げられており、日本の「医療マンガ」が扱ってきた領域のみに留まるものではない点に改めて注目してみたい。日本のマンガジャンル文化研究においても、「医療マンガ」ジャンルの扱い方はまだ模索の段階にあるものであるが、さらなる発展を遂げているエッセイマンガもまた、医療マンガやグラフィック・メディスンとの重なりを示しながらも、その枠組みを越えた展開を示している。
例えば、「生きづらさ」にまつわる多様な人生のあり方を描いた作品群は、「医療マンガ」との接点を持ちながらも、「医療」の枠組みでは捉えにくくなってしまうものもある。
グラフィック・メディスンの概念自体が医療者教育を担う医療人文学から起こったムーブメントであり、高度に専門化された医療の枠組みからこぼれ落ちてしまいかねない側面に光を当てることを目指したものであり、その成り立ちから包括的な概念であることが繰り返し強調されてきた。
時代を同じくして、日本でも社会学の分野から「生存学」の概念が提唱されており、「生・老・病・死」を軸に、やはり医療の範疇では収まりきらない側面を包括的かつ学際的に捉える取り組みが探求されている5。現在のエッセイマンガの発展からも「闘病エッセイマンガ」はそのなかで主要なサブジャンルを成しているが、「医療マンガ」が呼び起こすイメージでは捉えがたい作品をもあわせて扱う枠組みが今後よりいっそう求められることになるであろう。その点からも、グラフィック・メディスンの概念を踏まえたうえでの「医療マンガ」ジャンル研究が有効になるはずだ。ストーリーマンガもあれば、患者およびその家族による自伝的側面を持つエッセイマンガ(ノンフィクションマンガ)もあり、さらに綿密な取材に基づき、フィクションとノンフィクションをあわせた表現も発展している。
KADOKAWAの新しいレーベル「シリーズ立ち行かないわたしたち」は、「見知らぬ誰かの日常であると同時に、いつか自分にも起こるかもしれない日常の物語」を特色として打ち出しており、なかでも「セミフィクション」の手法を一つの柱としている。原作:ぺんたん、マンガ:まきりえこ『母親を陰謀論で失った』(KADOKAWA、2023年)は、コロナ禍による社会不安から陰謀論に取り憑かれてしまった母親の変貌をつづった文章を題材にしたマンガ化作品であるが、一人称の視点の語りを、さらに別の描き手がマンガ化することにより個別の具体的な事例がより普遍的な広がりを持つようになっている。医療マンガ、グラフィック・メディスンの枠組みからは捉えがたいとされてきた作品の一つと見なされうるが、エッセイマンガ(コミックエッセイ)がフィクションとの境界線を乗り越えようとしている方向性、そして、「ライフライティング」の観点からのグラフィック・メディスンへの学術的注目の動向を参照するならば、「生きることを記述する」エッセイマンガ全般をグラフィック・メディスンの枠組みで包括する視座もこれから求められることになるのであろう。
月本千景『学校に行けなかった中学生が漫画家になるまで――起立性調節障害とわたし』(中央公論新社、2021年)は、中学生の頃に心身の変調をきたし、登校できなくなってしまった著者による自伝マンガである。眩暈や記憶の欠落に苦しんできた学生時代を振り返る回想録であり、猫の自画像で描かれている。登校時間になると寝床から起き上がれなくなってしまった経験をはじめ、同級生とのあいだでコミュニケーションをうまくとることができなくなったこと、突然、授業内容が理解できなくなったこと、周囲の皆と同じように過ごすことができない疎外感や焦燥感、自己嫌悪、孤立など、具体的なエピソードを交えてその時の「気持ち」が丁寧に描かれている。
当事者視点の心情が猫の自画像によるマンガによって丁寧に、かつユーモラスに表現されていることにより、同じ症例を抱えている人、家族、そして周囲が理解するうえで本書は多くのことを伝えてくれる。人生に対し悩み続けながらも表現を通して自分らしくあろうとする著者の姿勢はグラフィック・メディスンを体現している。

ミカヅキユミ『聴こえないわたし 母になる』は現時点で単行本化はなされていない作品であるが、著者自身による個人ウェブサイト「背中をポンポン」ほか、オンラインマガジン『ウーマンエキサイト』誌、雑誌『レタスクラブ』にて発表されているエッセイマンガである。生まれつき耳が聴こえない著者の視点から、耳が聴こえる子どもたちとの家族の日常生活について、あるいは、社会生活における不自由な側面についてなどをめぐり具体的なエピソードを軸に描かれている。生まれた時から耳が聴こえない状況は、治療を前提とする「医療の領域」や福祉的な「障害の領域」では的確に捉えきれない面があり、日常のエピソードを通して、聴覚障害者が実感する生活の不便な側面やその時々の気持ちが描かれており、皆にとって暮らしやすい社会をつくるうえで多くのヒントを提示してくれる。その点で、「医療マンガ」のカテゴリーよりも広義のグラフィック・メディスンが志向する方向性に近いといえるのではないか。
「医療マンガ」の枠組みでは捉えがたいが、グラフィック・メディスンの概念で扱われている主題に「グリーフケア」の観点がある。「30選」には幼い子どもとの死別を描いた作品が選定されている6。作品として表現することによって、生きた証と交流の日々を記録する試みともなるもので、描き手のさまざまな想いが込められており読み手の胸を打つ。
せせらぎ『旦那が突然死にました。』(エムディーエヌコーポレーション、2020年)では、夫の死によって、結婚4年目の日常生活がまったく別のものに変貌してしまう。仲良く暮らしてきた夫との珍しい諍いのさなか、仲違いをしたままの永遠の別れとなってしまった。痛切でありながらもユーモアを交えて描かれている点に特色があり、二人の子どもの育児に奮闘する日々をつづった『旦那が突然死んだので発達障害児を一人で育てることになりました』(竹書房、2022年)へと続く。何もかもすべてが変わってしまった後も当然ながら人生は続き、亡くなった夫も作品のなかで主要人物として生き続けている。

きむらかずよ『16歳で帰らなくなった弟』(KADOKAWA、2021年)は、著者自身の弟が交通事故で亡くなった日の回想から始まり、四人家族が三人に減って以降の、父と母、そして著者自身の変化をたどる。弟は16歳、著者は当時17歳の高校生で、事故の日、バイクで出掛ける弟に声を掛けようとして呼び止められなかった経験が「死ぬほど後悔していたこと」として描かれている。もしあの時こうしていたら、という後悔がずっと心残りとなってしまうことも、とりわけ事故によって突然身近な人を失ってしまった場合には起こりうることなのであろう。
上野顕太郎『さよならもいわずに』(2009〜2010年、『コミックビーム』連載)は、急逝した妻と過ごした最後の日々の回想を軸に、絶望の淵に陥った著者自身の心境を、言葉を極力排して表現している。ギャグマンガ家として定評ある著者による異色作として、ドキュメントコミック(ドキュメンタリーマンガ)とも称されるその実験的技法が高い評価を得ている。
喪失の悲しみや亡くした人物への思慕の念のほか、残された側が故人とともに生きた証を記録し、その物語を通して自身の新しい人生を探っていくことから、「グリーフケア」の観点もグラフィック・メディスンのなかで注目されている。
グラフィック・メディスンは医療や健康のあり方を別の角度から捉えようとすることを目指すものであるが、究極的、あるいは、本質的に、医療や健康のその先にある生きることすべてを対象とする射程にまでつながるものであり、実際にグラフィック・メディスンを推進するペンシルヴァニア大学出版局が2020年からスタートしたレーベル「グラフィック・ムンディ」は国籍を越え、医療の領域をも越えて、人間、社会、生態系にまで目配りしている。そのような巨視的で、包括的な視野を持ちながらも、具体的な作品群においてはグラフィック・メモワールと呼ばれる回想録が軸となっており、各々が固有の人生のあり方に立脚している。多様性という括りのなかで、ともすれば個の物語が埋没しかねない現代において、あくまで個の物語に軸足を置きながら領域を乗り越えようとする姿勢にグラフィック・メディスンの特色と可能性がある。
脚注
※URLは2023年4月25日にリンクを確認済み