令和6年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業報告会が、2025年2月25日(火)に国立新美術館にて開催・配信されました。メディア芸術連携基盤等整備推進事業では、産・学・館(官)の連携・協力により、メディア芸術の分野・領域を横断して一体的に課題解決に取り組むとともに、所蔵情報等の整備及び各研究機関等におけるメディア芸術作品のアーカイブ化を支援しています。また、アーカイブ化した作品・資料等を活用した展示の実施に係る手法等を開発・検討することにより、貴重な作品・資料等の鑑賞機会の創出、インバウンドの増加を図るとともに、アーカイブ及びキュレーションの実践の場として提供することで、今後のメディア芸術の作品等の収集・保存・活用を担う専門人材の育成を図っています。報告会では、本事業の一環として実施した4分野の分野別強化事業の取り組みが報告され、有識者検討委員からの質疑や助言が加えられました。また、事務局調査研究等の報告、「マンガ・アニメ等中間生成物の保存活用事業」の紹介も行われました。本稿では分野別強化事業のうちの「メディアアート分野でのコミュニティネットワーク構築準備」を取り上げます。
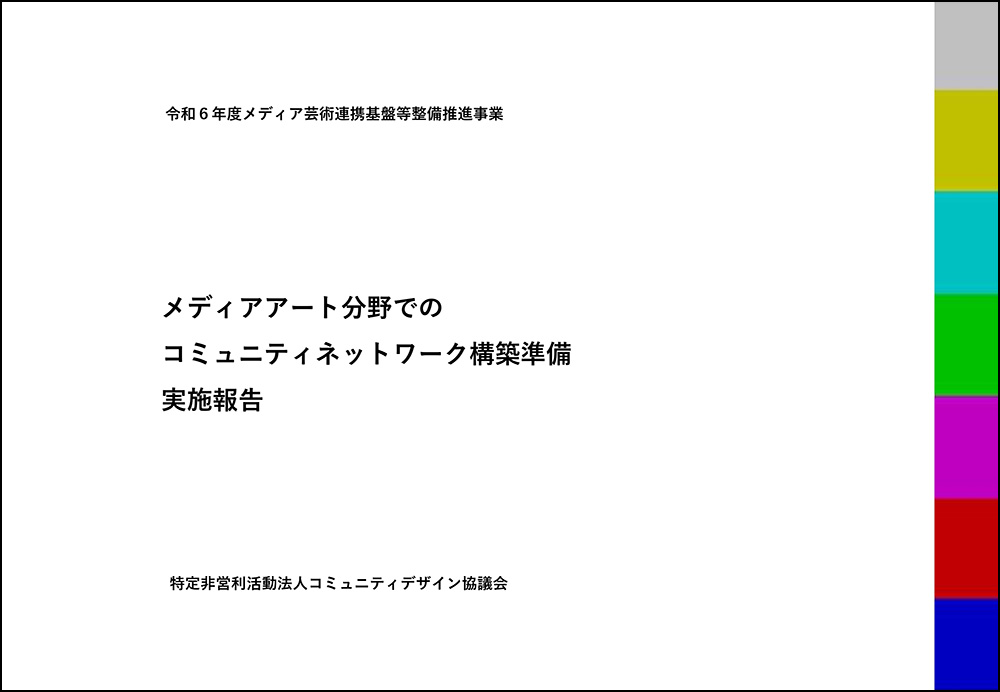
報告者:特定非営利活動法人コミュニティデザイン協議会 代表理事 野間穣
メディアアート分野では、日本のメディアアートの活動領域や作品が一般性を持っておらず、全体像の認知が低い点を考慮に入れ、多くの有識者や関係機関の協力を得て事業を行ってきた。実施体制はコミュニティデザイン協議会が主導し、調査、データの生成と整理、データやアーカイブの利活用、作品展示の記述項目策定、啓発活動、ネットワークの拡大を段階的に進めてきた。これらの事業の全体像を8項目に分けて報告する。
まず、①「調査」において、メディア芸術祭受賞者を含む多くの作家、関係者へのヒアリングを実施し、作品や資料の現状把握を進めると同時に、メディアアートを扱う施設、現代美術を扱う美術館やギャラリーの代表、担当者にも事業内容をヒアリングした。
次に、②「データの生成と整理」では、①「調査」の結果として、作家の提供資料からメディア芸術データベース(MADB)に登録できる作品データを作成した。
メディアアート作品がその形態や素材等が多様なことから、専門性を持った組織および関係者が資料を調査し、MADBのデータスキーム策定や作品データ、催事データの作成を行ってきた。さらに、メディアアートへの理解を促進するため、メディアアート史年表を制作した。
③「データの利活用」では、作成した年表をオンライン上で公開するとともに、国内外のメディアアートに関係する多数のイベントで展示。また、関係する学会でも年表の発表を行い周知を図った。その結果、年表の大学の授業での活用が進んでいる。
続いて、④「作品、資料のアーカイブ」では、すでに閉鎖された「キヤノン・アートラボ」の関連資料を整理し、保管方法のノウハウを公開した。また、故・三上晴子氏の作品や関連資料のアーカイブを構築するため、多摩美術大学が山口情報センターと協働し、作品や作品関連資料、講義資料などをデジタル化、オンラインでの公開を進めた。
加えて、⑤「アーカイブの利活用」では、三上晴子作品の修復を行い、インストラクションなど展示に関わる資料なども整備。今後も体験できる形での三上作品の展示が可能となった。
⑥「作品展示の記述方法提示」に関しては、メディアアート作品の保存、再展示、批評活動を支援するための包括的なプラットフォーム「PMA」の構築に取り組んだ。PMAは、関連組織への共有を目的とし、項目などの策定後に入力用アプリケーションを開発、マニュアルとともに配布した。これを活用し、アーカイブでデジタル化した数千点の資料が閲覧可能となった。
さらに、⑦「理解促進と啓発、継承」では、コミュニティネットワークのさらなる拡大を目指して、新しく計画されている関係施設や本事業での連携がなかった組織、これまでに数々の施設の立ち上げに関わったキュレーターのインタビューを行い、メディアテクノロジーを活用した表現に対する認識や課題をうかがった。また、ゲームエンジンやCADソフトなど活用し表現を行う若手作家、さまざまなジャンルを横断して活動する作家など、国内外で活躍する5名の作家にインタビューを実施。表現もツールもさまざまな作家に、作品制作に対する考え方や活動を続ける上での考えを聞き、本事業の取り組みについても意見交換を行った。
最後に、⑧「ネットワークの拡大と振興」では、国内外で評価されるような優れた作品の増加に寄与するとともに、関係するネットワークを広げ、作品の閲覧、展示、収蔵の機会拡大へとつなげていきたい。メディアアート領域は現在、多様なメディアテクノロジーの活用やジャンルを横断した表現などによって、より広範囲を対象とし、メディア芸術全般を横断する表現領域となっている。同時にメディアアートの重要性は増しており、社会や産業、技術との関係性が表現活動と密接に関わっている。
今後も、新しい技術や産業、メディアとのコミュニケーションを発生させ、表現活動へと発展させる状況を支援し、アーティストと社会、産業とマッチングする機会を本事業で提供していきたい。

※URLは2025年9月24日にリンクを確認済み