安原 まひろ
2020年にアニメーション作家のこむぎこ2000氏によって、個人制作アニメシーンの活性化を目的につくられた「自主制作アニメーション部」と、投稿用のTwitterハッシュタグ、「#indie_anime」。今も日々多くの短編アニメーションがこのハッシュタグをつけて投稿されています。このように、10年代から20年代に至る個人制作アニメーションシーンを俯瞰してみると、ウェブを介して個人制作の作家とそのファンがコミュニティをかたちづくることで、アニメーション作家が世に出る機運が生まれ、ミュージックビデオや短編アニメーション作品で活躍するようになった例が多々あります。こうした動向を踏まえたうえで、アニメーション研究者であり、「新千歳空港国際アニメーション映画祭」のプログラムコーディネーターでもある田中大裕氏に、「#indie_anime」の前後史を念頭におきつつ、現在の日本の個人制作アニメーションシーンについて話を聞きました。
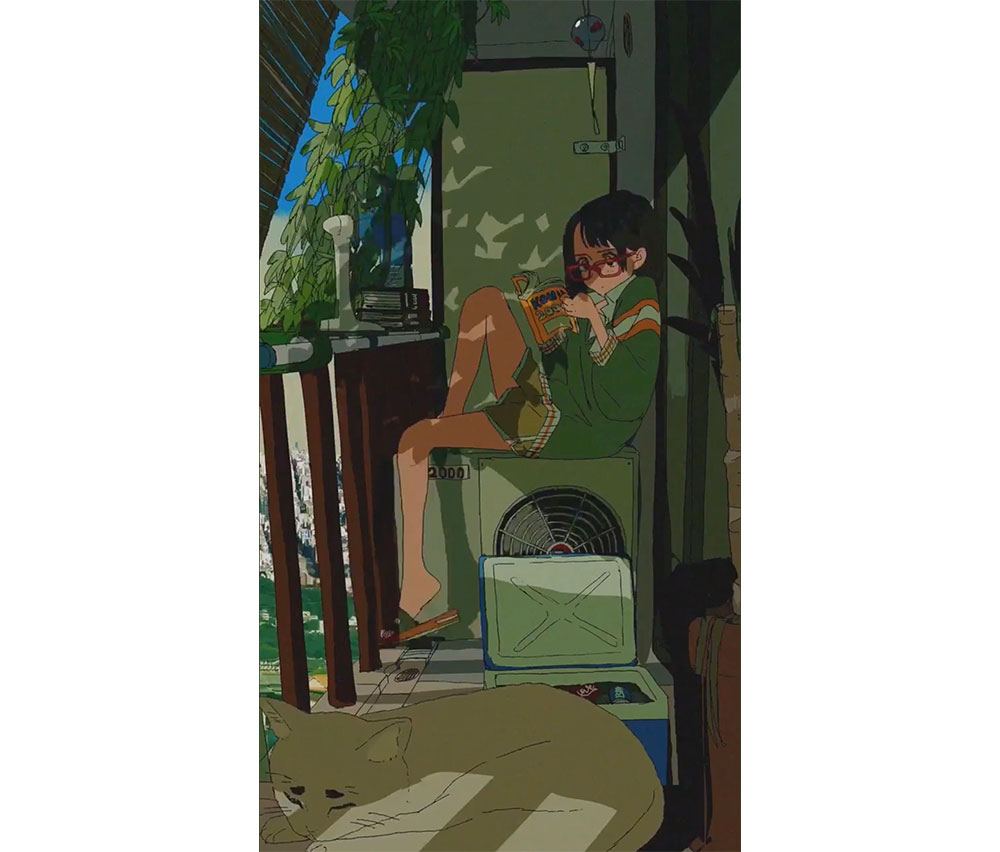
――まず、「#indie_anime」の前史的な話を整理できればと思います。SNSをはじめとしたウェブサービスを介して個人制作アニメーションを発表するという土壌がいかに形成されたのかについて、田中さんご自身の体験も踏まえつつお話をうかがえますでしょうか。
田中 私がまだ高校生だった2010年前後は、モーショングラフィックスやプロジェクションマッピングを使ったライブパフォーマンスが、ライゾマティクスの活躍によって国内でも広く一般に知られるようになった時期で、私にとっても原体験の一つです。当時、モーショングラフィックス関連の映像を手軽に見られるプラットフォームとして動画共有サービスの「Vimeo」が重宝されていました。Vimeoは「YouTube」に先行してHD画質に対応していたため、多くのビデオアーティストや個人アニメーション作家がVimeoで作品を公開していました。平岡政展さんや田島太雄さんらは、Vimeoから頭角を現した代表的なアーティストと言えると思われます。
ただ私見では、Vimeoはあくまでもファーストステップで、次のステップとしてコミッションワークや映画祭、芸術祭を想定しているアーティストが多かった印象があります。「DOTMOV」など、インターネット上の動向にキャッチアップする映画祭の存在も大きかったかもしれません。当時は、現在のようにSNSを介して幅広い客層に作品を届けられる環境ではなかったので、憶測ですが、インターネットをホームグラウンドとしてキャリアを完結するイメージが持ちづらかったのではないでしょうか。
Vimeoがほかの動画投稿系のウェブプラットフォームと大きく異なっているのは、「Staff Pick」というVimeoのスタッフが推薦作品をピックアップしてホーム画面に表示する、ある種のキュレーションが行われている点です。この「Staff Pick」を感度の高いアートディレクターや広告関係者がチェックしており、「Staff Pick」を通じて国内のアニメーション作家が、大きな海外案件の仕事を獲得するといった例もありました。キュレーションがしっかりと機能していたので、現在のSNSのように不特定多数に向けて発表するというような性格は薄く、実験的な作風であっても、きちんとしかるべき次のステップにつないでくれる場として機能していました。
また当時、Vimeoを介してつながった欧米圏のアニメーション作家によって形成された「レイト・ナイト・ワーク・クラブ」1という集団が、上映活動をしたり、オムニバス形式の新作を制作したりというような動きもありました。作家たちは画像やGIFアニメーション2を投稿するミニブログサービス「Tumblr」をうまく使って、自分たちの作品の断片をリブログできるよう工夫したりもしていました。こうした試みは、現在の「Twitter」や「Instagram」でバイラルを狙うことによって、より広い客層に自身の作品を届ける戦略の先駆けと言えるかもしれません。
いずれにせよ、10年代の個人制作によるアニメーションシーンは、芸術祭や映画祭などの既存のコミュニティと並走して、ウェブサービスを介したコミュニティも生まれてきた時代と言っていいと思います。もっとも、Twitterに動画を投稿できるようになったのが2015年の話なので、こうしたシーンについて語るためには、サービスごとの機能の拡充も念頭に置いたうえで、より精密に検討する必要があるかと思いますが。

――機能やツールという点では、ほかに10年代の個人制作アニメシーンにおいて特記すべき事柄はありますか。
田中 2015年にイラスト制作ソフトである「CLIP STUDIO PAINT」にアニメーション制作機能が追加され、2017年にはCLIP STUDIO PAINTがiPadへと対応しました。これ以降、iPadで完結したかたちによるアニメーション制作が可能になったわけです。また、2017年にはアニメーション監督の吉邉尚希さんが『ショートアニメーションメイキング講座』3という本を上梓しており、一からCLIP STUDIO PAINTでショートアニメーションをつくるための基本書として、広く読まれるようになりました。また、こむぎこ2000さんが学んだことでも有名になった、アニメーターの室井康雄さんによる通信教育プログラム「アニメ私塾」も重要です。2013年から「ニコニコ動画」やYouTubeで配信している動画コンテンツですが、これも作画の知識を学校に通わず独学できるという点で、シーンに大きな影響を与えたと思います。
こうした変化は、それまで主流だった美術系大学や専門学校で教育を受けてアニメーション作家になるというルートとは異なる、専門教育を受けずにアニメーションを独学するという流れを生み出しました。
アニメーション作家たちが活躍の場を広げるという観点では、ライブハウスやクラブも重要な場でした。VJ(ヴィデオ・ジョッキー)活動を通じて、アニメーション表現の実験を行ったり、隣接領域のアーティストとコラボレーションしたりすることで、活動の幅を広げたり、新しい仕事につながったりしていました。VJによる、アニメーション表現の現場としてですね。代表的な例を紹介すると、アニメーション作家の山田遼志さんは、King Gnu「Prayer X」のミュージックビデオで一般に広く知られる存在になりましたが、King Gnuの前身バンドの頃から協働してショーをつくりあげてきました。このように、ライブハウスやクラブの現場で築いたつながりが、現在の活動の礎になっているアーティストも少なくありません。
――以上のような個人制作が盛り上がっていった前史を経て、2020年にハッシュタグ「#indie_anime」が生まれ、SNSを中心により活発な作品発表が行われるようになりました。
田中 ハッシュタグを立ち上げた経緯について、こむぎこ2000さんは以前のインタビューで、自身がミュージックビデオの仕事を通じて得た知名度を自主制作の支援に還元したいと語っていました。そもそもハッシュタグ「#indie_anime」は、当初、それ単独で独立したものではなく、「自主制作アニメーション部」というこむぎこ2000さんが運用するアカウントで、このハッシュタグをつけて投稿されたGIFアニメをリツイートして紹介していくのがセットの取り組みでした。こむぎこ2000さんは、自主製作をしているもののまだ知名度が低い人をフックアップしたいという思いを持っていたようです。
「#indie_anime」において重要なのは、ハッシュタグをつけるだけでコミュニティに参加できるという、参入障壁の低さだと考えています。ご承知のとおり、新型コロナウイルスのパンデミックにより、ライブハウスやクラブ、美大などのフィジカルなコミュニケーションを前提とした場が機能不全になりました。リアルなコミュニケーションが喪失している状況のなかで、その代替として「#indie_anime」によるつながりが若手作家にとって刺激や支えになった可能性は高いのではないでしょうか。
――「#indie_anime」タグをつけて投稿される作品のなかでも、特に人気になる作品には一定の作風があるように思います。
田中 私見ですが、ハッシュタグ「#indie_anime」が前景化するスタイルの源流をたどると、細金卓矢さんによる、2013年に発表されたじんのボーカロイド楽曲「日本橋高架下R計画」のミュージックビデオにまで遡れるのではないかと思っています。こむぎこ2000さんがなぜ「バズった」のか、アニメーション関係者ともよく話すのですが、その一つの要因として、「日本橋高架下R計画」と同様に青とオレンジを基調とした、いわゆる「ティール&オレンジ」と呼ばれる色彩設計が考えられるのではないかと推測されます。ティール&オレンジは、2000年代後半あたりからハリウッド映画を席巻している色彩設計で、色彩学的にも理想的な組み合わせです。この色使いは、アニメーション作家のWabokuさんによる、2017年のEve「お気に召すまま」や2018年のずっと真夜中でいいのに。「秒針を噛む」のミュージックビデオなどにも共通しています。つまり、こむぎこ2000さんが広く支持を集めた理由は、単に現在の若者の気分に合致していたというだけではなく、理論的な裏づけが可能と考えるべきだと思います。
――「#indie_anime」は活性化しましたが、いっぽうで投稿数があまりにも多くなってしまい、検索性に欠けているという面はあると思います。
田中 先ほども述べたように、「#indie_anime」はハッシュタグ一つで誰もが簡単に参加できる風通しのよさに可能性と魅力があると考えます。反面、ご指摘のとおり、その手軽さゆえに検索性を損ない、鑑賞者にとってのガイドとしては機能していないのが現状だと思います。そういう意味では、「作画王グランプリ」や「#HashtagAnimeFes」「Project Young.」といったコンテストの試みは、厳選された良質な作品にアクセスできるという点で鑑賞者にとっては大変有益です。ただ、こうしたある種のキュレーションは権威化と表裏一体なので、違和感を覚えるつくり手もなかにはいるかもしれないと推察します。また、コンテストの審査員はクリエイターが大半で、キュレーターがいないことがほとんどです。誰しもに開かれてきたハッシュタグだからこそ、参加者のモチベーションや目的意識はさまざまなはずで、そうであるがゆえに、外部からの批評的な視点は受け入れられづらいのではないかと予想しています。
――アーカイブの問題もありますよね。SNSの性質上、投稿された作品はどんどん流れていってしまいます。
田中 私もアニメーション関連のアーカイブ作業にかかわることがあるのですが、アーカイブのための膨大な労力を考えると、現実問題アーカイブ化は難しいと思いますね。それに関しては、発案者のこむぎこ2000さんが「KAI-YOU」のインタビューで見解を述べていて4、アーカイブの有用性は認めつつも、スピード感ゆえの偶然的な「誤配5」を期待しているというような主旨の発言をしています。このあたりは、より瞬間的なアウトプットを重視したいつくり手と、長期的な目線でのデータベース構築を優先するリサーチャーとの価値観のギャップかもしれませんね。とはいえ、そもそも「#indie_anime」はつくり手によるつくり手のためのムーブメントである点は忘れてはならないと個人的には思っていて、あくまでもつくり手の目的意識を尊重するべきだと考えています。そのうえで、どういったバランスがありうるのかを検討していくべきなのではないでしょうか。
――Twitterにおける「#indie_anime」について話をうかがってきましたが、例えばInstagramで発表される個人制作アニメの動向はどうでしょうか?
田中 Instagramは、非常に重要な発表媒体になっていると感じています。海外のアニメーション作家がメインに使っているのはやはりInstagramです。日本国内のアニメーション作家に話を聞いても、Instagram経由で海外から仕事の依頼を受けるケースは増えているので、海外の仕事がしたいつくり手はInstagramを活用することをおすすめします。
――こうした動向を踏まえたうえで、田中さんは「新千歳空港国際アニメーション映画祭」では、どのようなコーディネートを行われていますか。
田中 今回の新千歳空港国際アニメーション映画祭における大きな変化としては、GIF部門の独立が挙げられます。これまでは短編部門でGIFアニメーションの応募を受け付けていたのですが、GIFでも応募できるということがじゅうぶんに認知されていませんでした。ですから今後は、GIFアニメーションという枠組みを新たに設けことで、従来の映画祭が取りこぼしがちだった作風の作品も積極的にフックアップしていく余地ができたと考えています。
参考にしたのは、アニメーション作家でレイト・ナイト・ワーク・クラブのメンバーでもあるジャネット・ボンズが中心になって立ち上げた、アメリカの「GLASアニメーションフェスティバル」です。小規模ながらもアニメーション関係者から信頼を置かれているフェスティバルで、GIFのためのコンペティションが設置されています。ハッシュタグをつけて「GIPHY」に投稿された作品をフェスティバル公式アカウントでシェアするというやり方を採用していて、インターネット上のコミュニティの巻き込みを行っています。
――誰もがハッシュタグをつければ作品を広く紹介できる時代において芸術祭に求められることは、やはりキュレーションなのでしょうか。
田中 作品がYouTubeで何百万再生されることには大きな価値があります。しかし、例えば50年以上前につくられたノーマン・マクラレンの実験アニメーションは、万人に受け入れられるものではないかもしれませんが、映画祭などで芸術的に高く評価されたことによって、現在でも世界中の映画祭や美術大学で繰り返し鑑賞され、世代を超えて多くの人々に届いています。それが10年、20年と雪だるま式に蓄積していけば、それこそ100万を遥かに超える再生数になるわけです。
そうした長期的な視点で作品を評価する専門的な目利きこそが、映画祭の価値であると考えます。また、それと関連して、同時代的な表現を歴史上に位置づけていくことも映画祭の使命ではないでしょうか。今回の新千歳空港国際アニメーション映画祭に関して言えば、国際審査員のひとりを、30年以上ニューヨークを拠点に活動しているビデオアーティストでありデザイナーのYoshi Sodeokaさんにお願いしていて、特集プログラムも組んでいます。Sodeokaさんは、Tame Impalaやマックス・クーパーらのミュージックビデオや、NIKE、adidas、Appleといった企業の広告を手掛けたことで知られていますが、インターネットが普及しはじめた1990年代には、最初期のオンラインマガジン「Word Magazine」のアートディレクターを務め、インターネットカルチャーの黎明期を牽引した生きた証人でもあります。日本では知る人ぞ知るSodeokaさんをいまこのタイミングでフィーチャーする意図は、それだけが理由というわけではないですが、ここまでお話ししてきたような日本国内におけるインターネット上のアニメーションシーンを歴史的に相対化する目的もあります。
また、これは私自身が映画祭にかかわっているのでポジショントークのように聞こえてしまう懸念もあるのですが、映画祭での上映や受賞をきっかけに認知され、国内外から仕事の依頼がくるようになるケースもあります。新千歳空港国際アニメーション映画祭に関しては、今では毎年2,000作品以上の応募があり、これは世界的に見てもアニメーション専門の映画祭としてはトップクラスの応募数なので、ノミネートだけでも狭き門ではあるのですが、今はオンラインで手軽に応募できる映画祭が大半なので、つくり手の方々は、新千歳空港国際アニメーション映画祭に限らず、さまざまな映画祭に挑戦してみてもいいかもしれません。
――「#indie_anime」に投稿を行うアニメーション作家が、今後短編のアニメーション作品などで活躍するような流れが生まれることはあるのでしょうか。
田中 基本的に「#indie_anime」に投稿されるアニメーションって、長くても2分程度の作品が多く、そこから10分前後の短編作品に挑戦するためには、越えなくてはならないハードルがいくつもあります。ご承知のとおり、アニメーションをつくるのは非常に労力を要するので。
また、先ほど制作ツールとしてCLIP STUDIO PAINTを挙げましたが、アニメーションとイラストレーションが共通のアプリケーションで制作される環境というのも重要であると認識しています。かつては「アニメーションは、絵を動かす芸術ではなく、絵で動きをつくる芸術である」というような、アニメーションの本質を運動の創造性に求める本質還元主義的なテーゼもしばしば唱えられてきましたが、今後は、まさしく「動くイラストレーション」とでも形容できるような、動きそのものよりも総合的なビジュアルや世界観、編集などに力点をおいた作品が増えていくと予想されます。「#indie_anime」で投稿されている作品を見ても、すでにそうした傾向は見て取れるのではないでしょうか。
しかしながら、アニメーションの芸術的価値を動きの豊かさに求める立場は、いまだに根強いように思われます。そうした立場からすると、「#indie_anime」のアニメーションの多くは「ぎこちなくて未熟」というふうに見えてしまいかねない。他方、映画祭でならば積極的に評価されるかというと、それもまた微妙です。映画祭では、動きを重視しない――ともすればほとんど動かないアニメーションであっても高く評価されることがあります。例えば、イギリスを代表するアニメーション作家の一人であるフィル・ムロイの「クリスティーズ」シリーズはその典型です。「クリスティーズ」シリーズは、シルエットで描画されたキャラクターの口パクが全編の大半を占める、極端にミニマルな長編テトラロジーです。おそらくシリーズ全体でもせいぜい数十枚しか作画していなのではないでしょうか? しかしながら、「クリスティーズ」シリーズのような作品が映画祭で高く評価されているのは、動かさないコンセプトが明確だからです。裏を返せば、動きが少ない芸術的意図が明確でない作品は、映画祭であっても評価されづらい。
何が言いたいのかというと、「#indie_anime」のアーティストたちがよりシアトリカルな短編アニメーション制作したとしても、現状、その受け皿となるのは動画共有サービスやSNSしかない。動画共有サービスやSNSを念頭に置くのであれば、コミッションでミュージックビデオなどをつくるほうがリアクションも期待できるでしょうし、アーティストのモチベーションもそちらに集中するのではないかと考えてしまいます……。「#indie_anime」のアーティストたちが短編アニメーションをつくることにより積極性を見出すためには、「#indie_anime」シーンのユニークさを文脈化して、作品の受け皿となるための場を増やすことが求められるのではないでしょうか。
――「#indie_anime」に投稿される作品が、世界的に主流となっている3DCGではなく、手描きアニメーションが多いことも、イラストからの延長線と考えると納得がいきます。
田中 そうですね。3DCG作品も少なくはないですが、おっしゃるとおり、2Dのほうが優勢な印象はありますね。アニメーターがイラストレーションも描く、イラストレーターがアニメーションもつくる、というようなどちらか一方に軸足をおいたある種の主従関係ではなく、アニメーションとイラストレーションが境界なく地続きなアイデンティティのあり方が、「#indie_anime」のアーティストたちには見て取れる気がします。
また「#indie_anime」の特徴としては、二次創作作品の多さも挙げられます。人気のアニメの二次創作をしてみたり、まだアニメ化されていないマンガをアニメーションにして動かしてみたり、といったような作品ですね。二次創作はまぎれもなくその人の作品ではありますが、完全なオリジナルではない。「#indie_anime」がそういった作品を気軽に発表できるプラットフォームであることも重要だと思います。イラストには「pixiv」のような投稿サイトがありますが、アニメーションにはそういう専用サイトがなく、YouTubeも検索性の面でいまひとつなので……。結果的に「#indie_anime」が二次創作アニメーションの投稿のハブとして重宝されているのかもしれません。
――「#indie_anime」を経たうえで、今後の個人制作アニメーションがどうなっていくのか、田中さんの見解を教えていただければと思います。
田中 複数の作家によるコラボレーションが増えていくのではないかと予想しています。例えば、ずっと真夜中でいいのに。の「猫リセット」のミュージックビデオのように、複数の個人アニメーション作家による映像をつなぎあわせて、一つの作品にまとめ上げるというものです。
「#indie_anime」に投稿しているアニメーション作家は、ミュージックビデオくらいの長さの作品をつくることが、技術的、あるいは時間的な制約で難しい人も多いはずです。だから、一人数十秒くらいの映像を組み合わせて、各自の作家性はキープしたままに統一感もあるユニークなミュージックビデオをつくるというのは冴えたやり方ですね。
「猫リセット」では12名の作家が参加しています。個性ゆたかな作家たちが一堂に会していますが、統一された一つの作品という雰囲気は維持されています。もちろん、アニメーションを見慣れた人であれば個々の作家の個性を識別できると思われますが、一般的には違和感なくスムーズに見られるのではないでしょうか。今後も、こういったプロジェクトは増えると予想しています。
こうしたつくり方は、うまくやれば尖った作家性とボリュームを両立できるため効果的ですが、個々の作家の持ち味を薄めてしまう懸念もあります。なので、個人作家のシーンにとって貢献的なのか、そうでないのかは、今後も注視していく必要があるのではないでしょうか。
――いずれにしても、新しい潮流の作品について論理的に言語化できる、キュレーション的な視点がやはり求められているような気がします。
田中 かつて、動画共有サイトが興隆してきた当時は、映画祭に代わるプラットフォームになると期待されていました。映画祭とは異なる評価基準のもと、映画祭では評価されづらいタイプの作品にも光が当たる場になると期待されていたのです。しかしながら、Vimeoのようなキュレーションに力を入れていたプラットフォームはYouTubeにシェアを奪われ、現在は、映画祭以上に「勝者総取り」的な状況が生まれています。
そういう意味では「#indie_anime」も、SNSで不特定多数に向けて開かれたムーブメントであるがゆえに、YouTube同様、「勝者総取り」的な傾向はあると感じています。ご指摘のとおり、多様な作品に目を向かわせる視座を示すためには、何らかのキュレーションは必要になってくると思います。とはいえ、先ほども述べたように、そうしたキュレーションをつくり手自身が望んでいるかというと、それは微妙だと思っているので、適切な距離感を見定めることが求められてくるのではないでしょうか。もっとも、「#indie_anime」のムーブメントが現在のアニメーションにおいて大きな意義を持つことに疑問の余地はないので、映画祭に関わる人間としては、どうにかしてキャッチアップしていきたいと考えています。
脚注
田中 大裕
コンピュータアニメーション史研究のかたわら、2018年より国内短編アニメーション総合情報サイト「tampen.jp」の編集長を務める。国内の短編アニメーションを紹介するライティングや個人アニメーション作家へのインタビューと並行して、上映イベントやトークイベントの企画・運営を行う。2022年より「新千歳空港国際アニメーション映画祭」プログラムコーディネーター。
※インタビュー日:2022年5月17日
※URLは2023年2月1日にリンクを確認済み