佐藤 恵美
写真:小野 博史
アーティストで研究者の久保田晃弘氏をナビゲーターに、次の100年に向けたアートとテクノロジーについて考える対談。テクノロジーと社会の関係について、人類学の観点から研究をする久保明教氏をゲストに迎えた後編では、前編に引き続き家庭料理を対象に「暮らし」をデザインできるか議論しながら、テクノロジーの話に展開します。会話型のAIであるChatGPTを生み出したニューラルネットワークを人間のアーキテクチャーの模倣物と捉えたとき、「ひらめき」や「アハ」などと呼ばれるような推論の能力は起こりえるのか、アルフレッド・ジェルの「アート・ネクサス論」を取り上げながら、話題を広げていきます。
連載目次
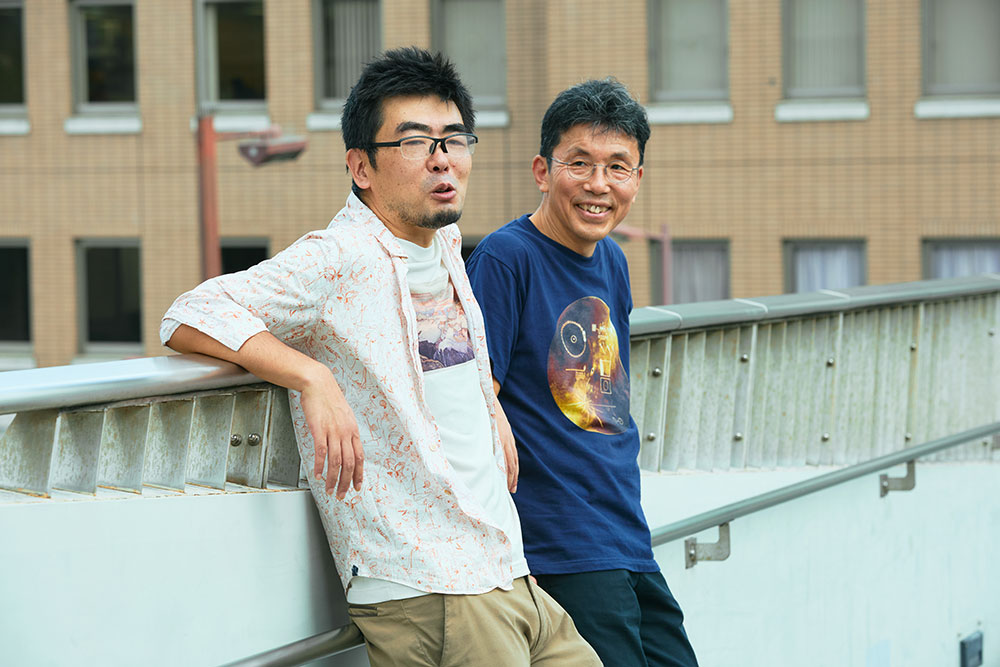
久保田 『ブルーノ・ラトゥールの取説――アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019年)でのモダン、ポストモダン、ノンモダンという区分を『「家庭料理」という戦場――暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020年)でも比喩として使っていましたね。
久保 かなり文脈が違うのであくまでアナロジーではありますが、いま自分たちがいる地点はもうポストモダニズムではないとしたらどう位置付けられるかという点で、『ブルーノ・ラトゥールの取説』と同じ図式が家庭料理の軌跡にもある程度当てはまると考えて採用しました。この本で中心的に扱っている料理研究家の小林カツ代さんや栗原はるみさんは、1980年代から1990年代に、それまで「これが正統な家庭料理のあり方だ」とされていたものを解体・再構築(脱構築)して、それ以前の「手づくりか手抜きか」の二項対立を乗り越えるような、時短とおいしさが両立するようなさまざまなレシピを広めています。
小林カツ代さんのレシピだと、例えば、本格的なワンタン料理から皮で肉を包むという過程を省略し、三角に切ったワンタンの皮と挽肉を一緒に煮てスープにする「わが道をゆく!わがままなワンタン」という革新的な料理があります。ただこれは、献立という意味では「主菜・副菜・ご飯・汁物」のうちの汁物であるという既存の枠組みにきっちり収まっているわけです。彼女のレシピ本の多くもそういう分類に沿って構成されていますしね。栗原はるみさんの本では、こうした枠組みも解体されて、焼いたサンマとレンコンと白米を炊きこんだカフェのワンプレートランチのような「サンマの洋風炊き込みご飯」とか、ワインともあうように生ハムやバジルを乗せた「レンコンのピクルス」のような、家庭料理をしゃれたレストランやカフェの料理へと近づけるようなレシピが提示されます。栗原はるみさんの本はキッチンやリビングでくつろぐ彼女の写真が多く使われていて、90年代に人気を博した主婦向け雑誌の名前を借りればそういった「すてきな奥さん」としての彼女の生活自体の魅力をレシピとともに味わえるようになっていますが、妻が夫や子どもに工夫を凝らしておいしいご飯をつくってあげるという旧来からの構図は温存されています。ポストモダニズムがどこかで「構築されていない真実」を想定しているように、彼女たちのレシピは「正統な家庭料理」との距離感によってその魅力を生みだしていたと考えられるのではないかと。
これが、2000年から2010年代、彼女たちのレシピ本を参考にしてつくられた料理を食べて育った世代が家庭料理を担うようになってくると、脱構築の標的であった「正統な家庭料理のあり方」自体が次第にぼやけてくる。そうすると、特定の料理研究家の権威や人柄や魅力によってではなく、レシピ投稿サイト「クックパッド」のような、多くの人が参照しているレシピがランキングの上位にあるということによってその有効性が保証されるような状況が生じてきます。Twitter(現X)で多くのフォロワーを持つ料理系のアカウントや、人気の料理系YouTuberのレシピについても同じことが言えるかと。「正統な家庭料理」との距離感によって規定されていたポストモダンな家庭料理よりもたしかに自由度は上っているし、すべてが構築可能であるとする汎構築主義的な発想が前面化してきた、という位置付けになります。
久保田 家庭料理に限らず、モダニズムが見直され、ポストモダニズムに移行していくと、常に自分の立場や意見を明確にしたり、主体的に行動するために、何かを選択したりしなければならなくなる。そんなポストモダニズムや汎デザイン主義を実践し続けると、栗原はるみさんの料理のように、見かけはリラックスしていて美しかったとしても、内実はだんだんと疲れてきてしまうことが多い。そう感じはじめると、ルールやモットーが明確なモダニズムや、人気ランキングのようなポピュリズムのほうがデフォルトで、そっちのほうが肯定的で明確に生きるための方策であるかのように錯覚してしまう。そうしたことを考えていたときに、内在的な「ノンモダニズム」の考え方は、何だかとても楽にしてくれる感覚がありました。楽になることは必ずしも悪いことではないし、苦しいこともけっして美徳ではない。常に仮説的かつ仮設的に、自分の思ったことや感じたことを、受け入れて実践してみることで、正直なものの見方や生き方ができるようになるかもしれません。
久保 ただ、これは「自分のやりたいことをやろう」といった表現が、1990年頃にはあくまで「自分がやるべきことをやれ」という体制的な発想に対するカウンターだったのに対して2000年代以降だんだん規範化してきた流れと並行していると考えているのですが、何でも自由にデザインできるという汎デザイン主義的な発想が浸透するほど、汎構築主義の受動性も高まってくるのではないかと。「自分のやりたいことをすべきだ」と言われるほど「自分のやりたいことって何だろう?」となっていくし、何でもデザインできると言われても「じゃあどの方向でデザインすればいいんだろう?」となる。その方向性を穏当に示すものとして、例えば「丁寧な暮らし」といった表現が魅力を持ってきたわけですが、これも「これは丁寧な暮らしなのだろうか?」とか「もっと丁寧な暮らしをすべきではないだろうか?」と考えはじめると、1960年代から1970年代の「手づくりvs手抜き」の二分法が生みだした「もっと手づくりすべきではないのか」という強迫的な観念とあまり変わらない苦しさがでてくる。
だから、モダン/ポストモダン/ノンモダンというのは必ずしも時代に沿ってパッキリ移り変わっていくものだとは考えていません。現状では、潜在的なレイヤーとしてはどれも並存しているし、モダニズムのレイヤーで培われてきたものはネットワークのかなり強力なハブであり続けているので、ノンモダニズム(汎構築主義)の立場で考えたとしてもそのあたりを組み替えることはそんなに簡単なことではないし、最初から組み替えられないものとして捨象されてしまうことも多々あると思います。

久保田 もちろん、入口が気楽になっても、高い山はどこに行ってもありますし、楽に生きることというのは、正直に生きることなのかもしれません。『「家庭料理」という戦場』を読んでいて、デザイン実践におけるリアリティを感じたのは、「デザインするぞ!」と意気込んでデザインしたとしても、大抵の場合、それは必ずしも優れたものにならないし、楽しいものにもならない。むしろ、つくりたくもない味噌汁をつくってしまったときこそ、そんな味噌汁をつくることを駆動したものは何か、という現実が顕在化してくる。つくることとつくらされることの中間領域に居続けることが重要なんだと思います。個性も同じで、自分の個性を出すぞ、と思って出したら個性じゃなくなる。隠そうと思っていても、出てきてしまうものこそが、肯定できるかどうかは別として、個性と呼べるようなものである。この本では、やろうと思わないのにやってしまうものごとのおもしろさと、あとやっぱり怖さを感じました。
久保 家庭料理の特徴は、そういうことが個々人を超えてなかば無意識的に引き継がれてしまうというところにあるかと。この本では、友人たちと一緒に小林カツ代さんと栗原はるみさんのレシピを基に実際に調理してどちらが好きか理由つきで述べるということをやった「レシピ対決五番勝負」を載せているんですけど、自分も含めてその人を構成するその人自身にも制御できないつながりがコメントからあふれでてきちゃうところがあって、楽しいけどちょっと怖い経験をしましたね。
久保田 その自分で制御できない部分こそが、本当に怖いですね。自炊を始めたときに、なぜか母親がつくったものに似た味になってしまったり、それを食べると懐かしかったりするように、思考も文化もすべてそうだと思いますが、無意識のうちに、さらに世代を超えて引き継がれしまうことの恐ろしさを感じます。「日本の」だとか「伝統の」という言葉でカモフラージュされていることも多いですし。
久保 家庭料理には、「手づくり」と「丁寧な暮らし」みたいに、過去の慣習や味や想いを忘れようと思ってもどこかでかたちを変えて復活してしまう面もあるし、似たようなことが繰り返されるけどいつの間にか忘れさられる面もある。学問の歴史とか技術革新のように「新しいものが出てきて旧来のものを乗り越える」みたいな歴史観とは違う、グチャグチャした歴史だと思います。
この本の参考文献に挙げている料理研究家の土井勝さんの本は、じつは自分の実家から持ってきたものです。母親がその本を参考にして料理をしていたので、今ふりかえれば、それを食べてきた影響が自分の今つくっている料理にもないわけではない。この本は、学問的な「分析する私」の参考文献として取り上げる以前に実生活における「暮らす私」の参考文献だったわけで、本文に参考文献として記載しながら不思議な気持ちになりました。でも、母親の米の研ぎ方は継承しませんでしたね。水を代えながら手早く数十回まわすんですが、自分もいつかこれができるようになるかなと思っていたし、やらなきゃいけないような気もしていたのですが、いつのまにか無洗米を使うようになってました(笑)。そういう「切断」が家庭料理史の至るところにあるのではないかと。でも米は研がないけど昆布や煮干しで出汁をとり、味噌汁もわりとつくってしまう。ゼミの学生に言ったら「なんですか? 丁寧な暮らしですか?」みたいに笑われるわけです。結構つらいですよね。「いや出汁とるのって意外に簡単よ?」とか言ったらますます嫌な顔をされます。誇りたい気持ちもあるけど「なんか不自由だなぁ」とも思います。過去をすっかり乗り越えるわけではなく、気づいたら同じようなことをやっていて、でも確実にズレも生じている。そういう暮らしの連続としての歴史のグチャッとした質感を、デザインと共立するものとして書きたかったわけです。それまでデザインという言葉が適用されていなかった領域にデザインという言葉を当てはめると、既存の前提とか構図を乗り越えられるかのように見えてきますが、デザインできるという発想が強まるほど、同時にデザインできないものが新たに生じてくるという感じですね。
久保田 「暮らしはデザインできるか?」という問いは同時に「暮らしはデザインできない」、なぜなら「暮らしはすでにデザインされている」から、ということでもあるんですね。読んでいると、すでにデザインされている部分の重さが浮かび上がってきます。なので、最初はおもしろく読み始めましたが、読み進めると、だんだん落ちこんできました(笑)。
久保 それは嬉しい感想ですね(笑)。自分も書きながら楽しいけどつらいような気持ちでした。どの辺が落ちこみました?
久保田 はい、それは先ほど述べたように、この話が「家庭料理」の領域にとどまっていないからです。20世紀は、数々の優れたデザイナーによって、生活が向上し、美的になり、称賛をあびました。そのモダニズム的な可能性が、未来をつくると吹聴された。ですが一方で、人間社会から競争や戦争はなくならないし、SNSでの中傷や炎上のような、自意識やコンプレックスの肥大化が起きている。デザインやアートを「称賛」に回収してしまうのは、とても危険です。そうしたことの意味が、この本を読み進めていくとだんだんと浮き彫りになっていく。称賛の危険性は、ウェルビーイングな暮らしのなかにこそ潜んでいる。ChatGPTのような会話型AIも、そうした丁寧な人間に似て、妙にポライトなのが気持ち悪いですね。

久保 僕がChatGPTをもう少しあとで考えたいのは、まだデザインされたてだからですね。「言葉を使って会話できる」ことが、人間とほかの存在の知性を区別する重要な境界とされてきたことを考えれば、ChatGPTはその境界を部分的に超えてきたように見えるし、人間的な知性の重要な部分とされるものが新たに機械的に再現・調整できるものとしてデザインされたと言えるのではないかと思います。今はそこで大いに興奮できますけど、興奮が冷めたあとに起こるのは、「わがままなワンタン」のその後とあまり変わらないようなグチャッとした軌跡なんじゃないかと。2014年に登場した「Pepper」も、初めて感情認識を実装したロボットとして私たちの生活や社会を変えていく「新しい」技術であるように当時は見えていましたが、9年後の今ふりかえって「Pepperは私たちの生活や社会をどう変えたのか?」と問われると全然よくわからないですよね。
久保田 僕もそう思います。慇懃無礼なChatGPTの口ぶりは、大仰な身振りのPepperになんだか似ています。そういうことをじっくり考えさせてくれるという意味で、この本はとてもいい本だと思いました。でもいい本だからといって、「よしやるぞ」っていう気にさせてくれるわけでもないし、「気分が晴れました」と思える本でもないのですが。
久保 書いているときは「笑い」をかなり意識してました。笑かそうとは思ってないけど、書いている自分にも刺さってきますし、ちょっと笑いながらでないと話せないようなことを語っている、泣き笑いのような文章だなと。古典的な意味での「喜劇」に近いのかもしれないですね。
久保田 この本を読んで、先日亡くなった小説家、ミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』(集英社、1989年)の読後感を思い出しました。主人公とその恋人であるトマーシュとテレザの二人は、紆余曲折を経て最終的には田舎に移住して一緒に静かに暮らしますが、それがけっして「ああ良かったな」だとか、自分も「こうなりたい」という感じでもなく、愛犬の安楽死とともに、淡々と静かに、でも何か衝撃的に物語は終わっていく。その感覚にちょっと近いかなと思いました。「家庭料理の耐えられない軽さ」なのかもしれません(笑)。
もう一つお聞きしたかったのは、『Art and Agency: An Anthropological Theory』(Oxford University Press、1998年)を書いた人類学者のアルフレッド・ジェルの「アート・ネクサス」についてです。ここでのジェルの議論は、今日どのように展開可能なのか。そして「アブダクション」について、久保さんは今どう考えていらっしゃるのか、ぜひ一度うかがいたいと思っていました1 。

久保 ジェルの「アート・ネクサス論」は、「インデックス」(指標)と「アブダクション」2というC・S・パースに由来する概念が軸になっているので、そこはラトゥールの議論との大きな違いだと思っています。アブダクションは基本的に人間による推論の能力だとされるので、人間が行うアブダクションが人間と非・人間の諸関係(アート・ネクサス)を構成すると考える限りは、人間と非・人間の対称性は確保されていないことになります。ただ同時に、実際にアブダクションがどう動くかはインデックスとして働く人間以外のエージェント(能動的な行為者)/ペーシェント(受動的な行為者)が人間のエージェント/ペーシェントといかに関わるか次第だともとれるので、そこはアクターネットワーク論の発想に近いと考えています。
通常のパース理解だと、アブダクションというのは特定の事実からそれを説明できるような仮説を形成する推論だとされます。「①意外な事実Cが観察された。②しかし、もしHが真であれば、Cは当然の帰結だろう。③よって、Hが真であると考えるべき理由がある」というかたちの推論ですね。これが、「Hが真であれば論理的に考えてCだけでなくほかの要素(D・E・F…)も事実である」という演繹や「D・E・F…が事実であることが確認された。したがってHは真であると言える」という帰納へとつながっていく。そう考えれば、アブダクションというのは演繹と帰納を通じて科学的に検証されうる仮説の形成に資するものだということになります。
ただ、このように言えるのは、諸要素(D・E・F…)が有限の範囲におさまっていて、その全域を見渡せるときです。ジェルのアブダクション概念はどうもそうなっていない。例えば、彼はインデックスが喚起するアブダクションの最良の例として、笑顔は好意のインデックスであり笑顔から好意が推論されるという例を挙げていますが、これは科学的に検証できませんよね。悪意があっても笑うことはできますし。「笑顔の裏にある好意」のようなインデックスが喚起するアブダクションは、客観的に検証されることがないまま実践のなかに組み込まれていく。CからHを仮定することは、Cという個物を超えていろんな要素を巻き込んでいくわけですが、そのすべてが自明の事実だと確定されることのないまま実践を駆動していく。そういう風にジェルの議論を捉えています。
久保田 たしかに、ジェルの考え方で非常におもしろいと思うのは、有限性の外部、あるいは非自明なものを取り込むのがアブダクションであるという点です。久保さんが言うように、狭く言ってしまうと、演繹は因果関係や三段論法のことになるし、帰納はChatGPTがやっているようなデータベースを用いた統計的手法になってしまいますが、アブダクションはそれらによってチェックできるもの、科学的に検証されうるものの外側にこそある。それはかつて「ひらめき」や「アハ」などと言うしかなかった。なので、その非自明な部分を、数学の穴、あるいはコホモロジーで表現できないかと思いました3。
例えばChatGPTを生み出したニューラルネットワークが、脳の生物学的モデルに由来する情報システムだとすると、そうした人間のアーキテクチャーの模倣物のなかでも、アブダクションは起こりえるのでしょうか。
久保 今のところChatGPTが何か新しいことをアブダクティブに推論しているように見えるときには、会話しているユーザーもともにその過程に参与しているように思いますね。
久保田 ツールのようなものと人間のハイブリッド、その複合体のなかでアブダクションが起きるということは、そのツールの上手な「使い方」の事例にはなると思うんですよね。でも最近は、そうしたアブダクションが、人間抜きの「他者」のなかだけで起こりえるのか。逆に起こったときにどうなるのかのほうに興味があります。よく、AIの出力を再帰的に学習し続けると、だんだんシステムが劣化していくと言われていますが、本当に劣化しかしないのか、創発(情報の生成)も起こりえるのではないか、と思ったりもしてしまう。少なくとも、将棋や囲碁の世界では、それが起こっているように見える。
2023年10月29日まで、レフィク・アナドルというトルコのアーティストが、ニューヨーク近代美術館(以下、MoMA)で「レフィク・アナドル:アンスーパーバイズド」(2022~2023年)というタイトルの展示を行っていて、議論を呼びました。200年以上にわたるMoMAの膨大な美術作品の画像データベースを教師なし(アンスーパーバイズド)学習し、そこから具象とも抽象ともつかないカラフルな画像を、リアルタイムに生成し続けるものです4。メディア批評家のレフ・マノヴィッチが、それに対して、おもしろいことを言っています。これは「過去を否定し、新奇なものを求めて更新し続けてきたモダニズム文化の成果をすべて無批判に受け入れることで、そこから惑星ソラリスのように、身近でありながら異質な、奇妙なものを生み出し続けている」と5。これもまた、ノンモダニズムの一つのあり方なのかもしれません。
そこでもう一度ジェルの話に戻ると、こうした大規模なデータベースから教師なし学習で生成されたものは、アブダクションなのか、あるいは単なるアルゴリズム的帰納なのかがよくわからない。ひょっとしたら、本当に創発現象が起こっているのかもしれませんし。
久保 僕が重要だと思っているのは、ジェルが「アート・ネクサス」を互いにエージェント/ペーシェントして関わりあうインデックス/アーティスト/レシピアント/プロトタイプの4項が織りなす関係として図式的に整理している一方で、それを生み出す「インデックスが喚起するアブダクション」を誰が/何が行うのかについては明確に定義していない、ということです。
ジェルとラトゥールを結びつけながら論じた2011年の論文を書いたときに自分が想定していたのは、アブダクションは存在者の諸関係(アクターネットワーク)自体に備わった力能であるという理解の方向性だったのですが、まぁ簡単に言えることではないですよね。アクターネットワーク論は構造主義以降の議論が注目してきた言語の多様な働きをうまくカバーできていないと思っていますし、いま書いている本では、人類学における「存在論的転回」の源泉とされるヴィヴェイロス・デ・カストロやマリリン・ストラザーンやロイ・ワグナーの議論を、レヴィ゠ストロースの構造主義をひっくり返して発展的に継承した議論として捉え直すことを試みているのですが、その試みが一段落したあともう一度ラトゥールの議論を変形しながら接続することで、他者性と言語の(特に比喩的な)働きを実装したアクターネットワーク論のような方法論を具体的な事例分析を通じて展開できるようになるかもしれません。ジェルの言うインデックスが喚起するアブダクションというのも、傀儡人形やマリア像といった人間がデザインしたはずなのに他者性を帯びる人工物の視点から人々が自らを捉えることによって諸関係があらかじめ特定できないものを生みだしながら拡張していく過程として捉えることもできますしね。
久保田 なるほど、たしかに誰がどのようにアブダクションを駆動しているのか、ということはアート・ネクサスにせよ、アクターネットワークにせよ、静的な図式の構造だけからは、なかなか見えてこない部分だと思います。冷蔵庫をあけたときに見える、残りものの食材が持っているエージェンシーかもしれないし、ネットワーク上に堆積した有象無象の無意味なデータそのものかもしれない。「人間がデザインしたはずなのに他者性を帯びる人工物」という視点も重要だと思います、半デザイン、半他者の存在物が入り乱れた複数の世界を行き来しながら、常に暫定的にものごとを考えたり考えさせられたり、何かをつくったりつくられたりしていく。それが有限の、でも多元的なノンモダンの世界で生きる=アブダクションするということなのかもしれません。いや、むしろそうであってほしい。次のご著書も、とても楽しみにしています。

脚注
久保 明教(くぼ・あきのり)
1978年生まれ。一橋大学社会学研究科教授。大阪大学大学院人間科学研究科単位習得退学、博士(人間科学)。科学技術と社会の関係について文化・社会人類学の観点から研究を行う。主な著書に、『現実批判の人類学――新世代のエスノグラフィへ』(世界思想社、分担執筆、2011年)、『ロボットの人類学――二〇世紀日本の機械と人間』(世界思想社、2015年)、『機械カニバリズム――人間なきあとの人類学へ』(講談社、2018年)、『ブルーノ・ラトゥールの取説――アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019年)、『「家庭料理」という戦場――暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020年)など。
久保田 晃弘(くぼた・あきひろ)
1960年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース教授/国際交流センター長。アーティスト。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学に関する研究を経て、1998年より多摩美術大学にて教員を務める。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。著書に『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(BNN新社、2017年)、共著に『メディアアート原論』(フィルムアート社、2018年)ほか。
※インタビュー日:2023年9月11日
※URLは2023年11月15日にリンクを確認済み