佐藤 恵美
写真:畠中 彩
アーティストで研究者の久保田晃弘氏をナビゲーターに、次の100年に向けたアートとテクノロジーについて考える対談シリーズ。パフォーマンス制作もしながら東京大学大学院で教鞭をとる中井悠氏をゲストに迎えた対談後編では、デーヴィッド・チュードアの作品を起点に、「影響」と「コントロール」とメディアアートの関係を考えていきます。SNS上の影響力について話題になることも多い私たちの社会で、中井氏のとるアプローチはどのようなものなのでしょうか。
連載目次

久保田 中井さんの本を読んだり、お話を伺ったりしていると、ジョン・ケージよりデーヴィッド・チュードアのほうがおもしろいと思えてきます。
中井 ケージは良くも悪くも弁がたつし、いろいろなものを代表する立場を自ら引き受けてしまったがゆえに、言葉で自分のやっていることを説明するということをやり続けた人でした。でもそのことで、ケージが持っていたラディカルな部分が見えなくなってしまったようにも思います。一方で、チュードアはケージと活動をともにしながら、あるいは活動をともにしていたがゆえに、かなり意識的に自分のやったことについて語ったり書いたりしていない。だから、いまだに組み尽くせないポテンシャルを感じるんです。
久保田 なるほど。人は有名になればなるほど、社会はシンプルなイメージを求めるので、ケージもそこにはまってしまったのかもしれません。「4分33秒」があまりにも有名になり、記号化したことで、そのほかの普通の作曲の良さが、逆に覆い隠されてしまったようにも思います。
中井 「4分33秒」は、毎回の演奏はもちろん、それぞれの聞き手によっても聞こえる音が違うという不思議な音楽です。だから、そのつどのスペシフィックな演奏で耳にされる個別の音に力点が置かれていたはずです。でも、ケージが語った作品のからくりと「沈黙」の概念があまりにも有名になったために、皮肉なことに実際に耳にしたことがなくてもみんなが語れる作品になってしまった。ところが、初演をしたチュードアはどうやら、この「4分33秒」の逆説に密かに不満を抱いていたようなんです。
チュードアとケージの最後のコラボレーションは、振付家でダンサーのマース・カニングハム(1919~2009)の「Ocean」(1994年初演)というコレオグラフィーの音楽でしたが、制作の途中で、カニングハム・ダンス・カンパニーの音楽監督だったケージが亡くなりました。その役を引き継いだチュードアは、いろいろな知り合いに「海に関連する音を集めてきてほしい」と頼み、集まった録音を音源として演奏する「Soundings: Ocean Diary」という音楽をつくっています。1996年に亡くなったチュードアにとっても、最後に手掛けた重要な音楽なんですが、正直なところ、「Ocean」だから「海に関する音」を集めて演奏するというのは、何だかすごく安易でつまらないアイデアだと思って、本では取り上げなかったんですね。
でもそのあとの研究でわかったことがありました。モリー・デーヴィスという映像作家がちょうど1994年にチュードアのドキュメンタリーをつくろうと撮影していた映像があって、それを本人にインタビューしたときにもらったんです。それは「Ocean」のセットアップをずっと写しているのですが、同じカニングハム・ダンス・カンパニーの音楽家であった小杉武久さん(1938~2018)がやってきてチュードアと二人で話すシーンがそのなかに出てくるんです。それで小杉さんが、これはどんな曲かと聞くと、チュードアは「知り合いに『海の音』を集めてほしいと頼んだから、クジラの音などが集まってきたけど、自分が本当にほしかったのは『海の音』を録音しようとするときにたまたま録音されてしまう音だった」と言うんです。そして、そのような音を「peripheral sound(=周縁の音)」と呼んでいる。
ケージとの最後のコラボレーションであったことを踏まえると、これはチュードア流のケージへのオマージュだと思うんです。つまり、ケージは意図や目的から外れる副産物としての音を「沈黙」と呼んだわけですが、それについて語りすぎたため、今度は「沈黙」が概念として一人歩きし、目的化されるようになってしまった。それをずっと隣で見ていたチュードアは、「peripheral sound」という概念を語るのではなく、「『海の音』をとってきてほしい」という仮の目的だけを知り合いに伝えたわけですね。でもさらに奇妙なことがあります。なぜなら、小杉さんとのこのシーンが撮影されたのは、すでに「Ocean」の公演をチュードアと小杉さんの二人の演奏で何度か終えたあとでした。つまり小杉さんが今さらこんなことを尋ねるはずがないんですね。だから、カメラがまわっていることを念頭に置いた芝居のように思えてくる。外からは観察できない隠れたからくりの存在を仄めかすマテリアルを残し、僕のような研究者がモリー・デーヴィスにコンタクトを取ると、この作品を解読するために必要なパズルのピースが入手できるように仕組まれているようにすら感じる。そのことについてのエッセイを昨年ザルツブルグで行われたチュードアの回顧展のカタログに書きました。
久保田 チュードアはパズル好きで知られていますよね。チュードアにひいてもらうために、パズルとしての楽譜を残した作曲家もいたように、今度は逆にチュードアの残したパズルを中井さんが解いたのですね。
中井 ケージはチュードアがパズルを解くことだけではなく、つくることに関しても天才的だったと述べていますが、1940年代のレシートまで丁寧に保存された膨大なアーカイブを見渡すと、人生をかけて巨大なパズルを残したように思えてくるんです。ただし重要なのはそれが本当にパズルであるかどうかではなく、パズルであるという仮説を立てると、資料の膨大さに尻込みすることなく、やる気が出てくるというパフォーマティブな次元なんですね。

久保田 今の「Ocean」のお話は、メディアアートを考えるためにも重要なポイントだと思います。コントロールし過ぎてしまうと、インタラクティブアートにはならないわけですよね。作家の意図どおりに体験者を動かそうと思ったら、それはインタラクションではなくコントロールです。チュードアもあえて意図を伝えずに、集まったものをすべて受け入れた。そこが重要なのではないでしょうか。
中井 そうなんです。だから最近は目的を追求するプロセスにおいて生まれる「副産物」の働きを多角的に調べる「副産物ラボ(s.e.l.o.u.t.)」という研究室をやっています。そもそもなぜ「影響」に関心を持ったかというと、チュードアは人間と楽器の関係や、楽器と楽器の関係など、不確定性を含んだ作用を言い表すために、「control(制御)」という言葉に対置させながら「influence(影響)」という言葉をよく使っていたんですね。コントロールできないという不確定性が影響の根幹にあるのは、先ほども言ったようにそれが受け手側において成立する概念だからです。例えば制作したものを不特定多数に向けて公開するのは、それを受け取ってくれる人が出てくるだろう、という希望に基づいていると思うんです。でも、そのような遅れてくる観客とは、自分が思ったとおりのことではなく、思いもよらないことを引き出すだろうし、それを確定的にコントロールすることはできない。だから未来の受け手において成立する影響関係とは、つくり手が想定した目的よりもそこから外れる副産物に関わるんです。
久保田 中井さんは、その「影響」をどのような方法で研究されているのでしょうか。
中井 実践的な部分では、自分があまり得意ではない協働作業をあえて積極的にやっています。思いどおりにならない他者との関わりを高めることで、予想外の副産物がより多く発生するようにしたいんです。あとはチュードアの「海の音」のように、「影響」という概念を目的として掲げたときに、それがどのような副産物を影響として生み出すのかも観察しています。でもそうしたことはやはりあまり語らない方がいいので、自分一人でやっている範囲の研究に話を絞れば、例えば「影響」という概念自体の作用史について調べています。日常会話でも学術論文でもそうですが、「影響」は、作用関係があるけれどうまく言い表せないときや、複合的すぎて厳密に記述できないときに誰もがつい無意識に乱用しがちな言葉です。もともと中国語における「影響」は、時間的方向性を持った「作用」ではなく「関係性」の意味合いに近かったのですが、日本で「influence」の和訳を「影響」としてから、それが中国に逆輸入されたようです。
一方で、英語の「Influence」の由来をたどると、古代の占星術に行き着きます。語源であるラテン語の「influentia(流れ出るもの)」は、星々から地上に降り注ぐことで、いろいろな事象を左右する力の流れを指していました。あらすじだけを語れば、影響という考えは、そうした力の流れに介入する「魔術」という実践とともにルネサンス期に大々的に復活したものの、17世紀のいわゆる科学革命でいったん廃れるように見えます。でも特にイギリスでは、1600年に『磁石論』を書いたウィリアム・ギルバート(1544~1603)をはじめに、影響論の延長線上に電力や磁力や引力など遠隔で働く力に対する研究がニュートンに至るまで活発に展開されていく。さらに18世紀半ばには、卒論でルネサンス期の影響論とニュートンの万有引力論の接合を試みたドイツの医師フランツ・アントン・メスメル(1734~1815)がそのような研究を踏まえて、生物の間で作用する「動物磁気」に基づいた精神の治療法を開発します。この動物磁気はヨーロッパで大ヒットしたのですが、ベンジャミン・フランクリンを団長とする科学者の調査団によって、そのような力は物理的には存在しないと結論づけられるんですね。ただ、それで話が終わると思いきや、物理的には存在しないものの、精神の病が治るという効果が実際にあったとすれば、それは「想像力」にとてつもないポテンシャルが宿っているからだという風に理解され、メスメリズムは余計に人気を集めてしまう。その流れで生まれた催眠術など、想像力に働きかけて人を遠隔操作するさまざまな技法はそれからアメリカに伝わり、奴隷をプランテーションで働かせたり、女性の労働者を工場で働かせたりなど、他者の振る舞いを制御するために使われるようになります。ただしその一方で、催眠術にかけられる側は、かかったふりをすれば好きなことを言えるので、その立場を逆手にとった抵抗が生まれてくるんですね。例えば、19世紀後半の心霊主義において霊媒師のほとんどが女性だったのは、女性の方が意思の力が弱いというジェンダー差別が土台になっていました。でも霊媒師の方は霊に憑依されているという設定のもと、それまであまり公にできなかった女性の権利について積極的に語るようになり、それが19世紀の女性解放運動に連なっていくという重要な歴史があります。そして20世紀になると、心霊主義と裏表の関係にある心理学から生まれた行動主義や精神分析を介して影響の力学は広告業界に流れ込んでいき、それが回り回って、インフルエンサーという不特定多数の他者の振る舞いを遠隔操作する新手のビジネスに至っている。
久保田 現代も、「影響」という言葉がSNSやインターネット広告で頻繁に使われる一方で、ユーザーもあえて、そこに便乗するふりをして好き勝手に発信するような面もあり、まさに両義性がありますね。そうした歴史をたどっていくのは、チュードアの言った「peripheral」なものとして、とても重要なことだと思います。
中井 このように最近はチュードアの研究から出てきた副産物を軸にしながら、それを別方向に展開する研究を進めています。もう一つ事例をあげると、チュードアは楽器の固有性を語るときに「bias(バイアス)」という言葉を時々使っています。日常会話で「バイアス」というとネガティブに聞こえますが、電子工学では、回路を上手く作動させるために付け加える電流や電圧のことを指します。でもこれは日本語に訳すのが難しい言葉なんですね。「偏り」だと「bias」が持つ意味の広がりを捉えることができない。それでいろいろと考えた末、「癖」という言葉がいいんじゃないかと思ったんです。「癖」は「habit」と訳されることが多いですが、「bias」とは真逆に「habit」だと「癖」が日本語で持つ意味の広がりを捉えることができない。例えば「寝癖」というのは「habit」とは言わないわけです。じゃあ「寝癖」をモデルに癖一般を考え直すとどうなるか。「寝癖」というのは、眠っているときに寝具と自分の頭の間で起こった接触が身体側に偏りとして記録される現象です。そして、「口癖」や「思考癖」なども一緒にいる人や読んだ本との接触において感染したりする。だから、個人の癖のネットワークをその人が生きてきた固有の経歴のなかで蓄積された世界との接触によって造形された記録集として考えることができる。でも、マイクロターゲティングのような広告原理を実現する各ユーザーの行動パターンのモデリングは、要するにこのような固有の経歴と偏りから予測と制御を生み出そうとするわけですね。だから癖の問題は影響の問題に結びつきます。ただし、「行動」と訳されがちな「behavior」をあえて「振る舞い」と訳すことで、行動=振る舞い主義に対する抵抗をダンスの問題として組織化できないかなと考えているんです。そこで、「アルシ・コレオグラフィーズ(原振付)」というタイトルで、人間の癖を振付の問題として見る、拡張されたダンスの授業を始めました。
久保田 具体的に、それはどのような授業なのですか。
中井 ダンスを新たにつくり出すのではなく、それぞれが気づかないうちに従っている振付に焦点を当てることで、引き算的にダンスを発見する試みです。人間の癖のタイプは大きくは三つくらいあって、一つは自覚している癖、二つ目に自覚していないけれど他人が気づいている癖、三つ目に自分も他人も気づいていない癖です。この最後のタイプは、例えば高齢になって腰を痛めて病院に行くと、「長年の歩き方のせいだったのか」と事後的にわかるようなものですね。授業では、初めに「自覚している癖」について自己紹介してもらいます。でもその様子を撮影して、みんなで分析すると、自覚していない癖がダダ漏れていることに気づくんですね。もちろん分析する人によっても、発見する癖は変わってくるので、その次にそれぞれが提出した分析自体に含まれる癖を分析していく。要するにそのつど仮の目的を与えながら、そこから生み出される副産物を互いの観客として回収して、次の分析対象にすることで、逃げ水のような性質を持つ癖という現象を捉えようとするんです。
久保田 自己言及的でもあって、おもしろい授業ですね。どうやって癖を分析するのですか。
中井 最初はそれぞれの発表の映像やレポートの筆跡などを互いに観察して、それをさらに発表やレポートにまとめたりするのですが、途中から映像解析ソフトなどを使って、もっとミクロなレベルで、呼吸やうなずきのタイミングなどを詳しく見ていきます。特に重要なのは、言語学でフィラーと呼ばれる「えーと」とか「あのー」とか、会話の隙間を埋めてリズムを整える発話です。ある程度それぞれの癖が抽出できた時点で、それぞれの学生がほかの学生のなかから一人ターゲットを絞り、その人の癖を自分に移植したりしていきます。そして、最後に「『約3カ月間、いろいろな癖を見てきてわかったことを、レポートにまとめてみんなの前で発表してください』という課題が出されたらあなたのターゲットはどのような発表をするか」という課題を出します。
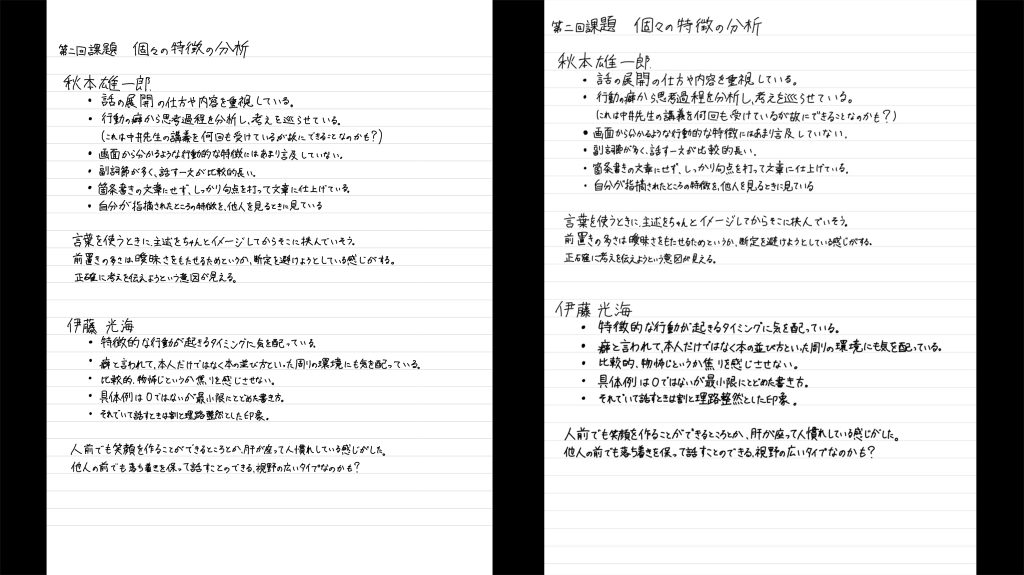
久保田 その人に代わって癖を再現するのですね。その授業は、ぜひ拝見してみたいです。中井さんがユニークなのは、ターゲットしたテーマの外側の視点を常に持っていることだと思いました。非常に重要なアプローチだと思うけれど、なかなか多くの人が持てるものではない。今のような「影響」へのアプローチを、ぜひもっといろいろなところで語っていただきたいです。
中井 でもあんまり話すと、ケージのようになってしまうので……(笑)。
久保田 確かにそうですね。でも今回の話は残るので、いつか誰かが中井さんのパズルに気づいてくれるといいなと思います(笑)。
中井 現在のインターネットやSNSについて批判的になりがちですが、未来に関してどこか楽観視している面もあるんです。日本語だと手垢がついた言葉で、語弊を生む可能性もあるけど「愛」のことを考えると希望が持てると思うんです。例えば僕にとって、自分の子どもが一人死ぬことは、知らない人が何人も亡くなることと比較しても、まったく違う重みを持っています。ケージの「沈黙」と同じくこういう原理的に一般化できないことは、言葉で語ると危ういのですが、あえて言えばSNSにおける関係性の数値化は、愛のような一般化できない関係を見えなくさせてしまう。でもおもしろいのは、FacebookやInstagramなどの開発に若い頃関わった人たちでも、30代になって自分の子どもができたりすると、一転してそのようなシステムを批判しはじめることがある。
久保田 スティーブ・ジョブズ(1955~2011)も、自分の子供にiPadを使わせることに慎重になっていましたよね。
中井 そのiPadをうちの子が住む世田谷区では小学校で配っているんですけどね(笑)。でも、未来の受け手について考えるようになったきっかけは子育ての経験でした。子どもに対しては、こちらがいろいろと思って何かをやっても、思いどおりのレスポンスが返ってこないことがほとんどですが、その代わりに思いもよらなかったことを引き起こしたり、予想外のところにつながったりしていく。でもだからと言ってすべてを偶然に任せるわけにもいかない。こうして子育てをしていると、そのつど立てる目的と、そこに回収できない子どもという他者を介した副産物との時間差が前景化しますが、そこにおいて影響の力学と愛の問題が重なり合うと思うんです。
久保田 愛に加えて信頼や責任も重要ですよね。これらも一般化できませんし、相互につながっています。とはいえ技術的にできることもあって、TwitterなどのSNSも、フォロワーの数の上限を、例えば1,000人くらいに限定するだけで良い。地球環境もそうですが、有限の中で考えることが、今の時代には必要です。
中井 そうですね。そして、その有限性は1,000人がそれぞれ具体的に誰であり、誰でないのかという個別性の次元にもつながる。そういえば、この対談も僕の本を手にとってくれた読者の一人がたまたま久保田晃弘さんだったことから始まっているわけですね。

中井 悠(なかい・ゆう)
東京大学大学院総合文化研究科准教授。四谷アート・ステュディウムで研究・制作、東京大学大学院で修士号、ニューヨーク大学大学院で博士号を取得。No Collectiveのメンバーとして音楽、ダンス、演劇、お化け屋敷などを世界各地で制作。出版プロジェクトAlready Not Yetとして実験的絵本やことわざ集などを出版。最近の著書にデーヴィッド・チュードアの研究書『Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』(Oxford University Press、2021年) や、チュードアの未発表音源を収めた2枚組LPと論考『Monobirds/When David Tudor Went Disco』(Topos、2021年)など。最近の作品に、Zoomを固有の楽器として捉えるzoomusicという架空の音楽ジャンルなど。
久保田 晃弘(くぼた・あきひろ)
1960年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース教授/国際交流センター長。アーティスト。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学に関する研究を経て、1998年より多摩美術大学にて教員を務める。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。著書に『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)、共著に『メディアアート原論』(フィルムアート社、2018年)ほか。
※URLは2023年3月1日にリンクを確認済み