秦 亮彦
企画・ファシリテーション:一條 貴彰
映像・音楽・ストーリーテリングなど多様な芸術要素が統合されて生まれるゲームという表現を、制作者の声で紐解く本シリーズ。前編に続く後編では、ドット絵を用いたインディーゲームを開発するウマー氏と小林光氏に、開発時の工夫やプロモーションなどについてうかがいました。
連載目次

――続いて、個人開発の工夫についてお聞きします。小林さんは『エレマスタ』(2019年~開発中)の構想はなんと20年にも及んだのですよね。
小林 制作は20年ずっとではなく、間が空いていて考えて挫折したりしているので、実際は5年くらいです。きっかけは『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(1988年)で、オープンワールドではないけど世界を旅するのが楽しいという体験をしたことです。ただ、オープンワールドに挑んで挫折したりして、もう一度知見を集めてから再度チャレンジしました。
長期プロジェクトの継続方法ですが、どんなに疲れていてもツールを立ち上げて木を一本でも植えることが大切と思っています。へとへとになっても絶対ツールを立ち上げて、「今日もやった」という既成事実を日々、積み重ねることですね。
進め方の意識としては、元気なときにはタスクを積み、疲れたときにルはーチンワークをしたりします。例えばこのエリアに木を植えるだけなら疲れていてもできるので後回しにします。それから作業配信もやっています。配信すると、他人の目に触れる緊張感もあって無理にでも進められるんです。SNS配信は決まった時間にやると決めていて、これが小さなマイルストーンになって、やることが決まっていく。そして、決めたらやるマインドで取り組んでいます。
ウマー 『Fishing The Abyss』(2024年)のような小規模なゲームをつくろうと思ったきっかけは、『Remain On Earth』(2018年~開発中)の開発が長期化してきたことです。当初の計画の段階で既に長期化することは想定していましたが、実際に時が経ってちゃんと完成させるための計画を立て直す必要があると思ったんです。そのために実際のゲーム開発から販売、アップデートしていくまでの流れを一通り経験する必要があると考えました。なので『Fishing The Abyss』が長期化して本末転倒にならないように、開発期間は最大でも半年と最初から決めていました。
――開発のノウハウの蓄積が目的だったのですね。それで長くても半年と決めていると、開発のなかでやりたかったができなかったことや取捨選択したことはありますか。
ウマー 私がやりたいことは『Remain On Earth』のような小規模だとやりきれない壮大な計画だったので、小規模開発の特徴である「人も時間も少ない」という制限が、やりたいことの足かせにしかならないと無意識に思い込んでいたんです。
でも実際に小規模ゲームの開発をやってみて、そういった制限こそが小規模開発のミソの部分と感じました。普段はやらないような徹底したコスト削減を行っていくなかで、コストを削減しつつもより効果的に見せることのできるアイデアや意外な結果が生まれました。ちょっとしかゲームをつくったことのない人間が言うのもなんですが、小規模開発が大規模開発に勝るとも劣らない独自性は、この制限の中だからこそ生まれるのかもしれないと思いました。
例えば、『Fishing The Abyss』は生き物が222種類いるのですが、生き物を釣って収集するような要素があるゲームには図鑑画面があって、そこには生き物の名前や説明文が載っているのが一般的なイメージじゃないかなと思いますし、おそらくみんなそれを期待するのがわかっているので私の場合は通常なら絶対入れようとします。でも、222種類の名前と説明文を一つひとつ考えるのはコストが掛かると思ったので、生き物の名前の設定をそのとき付けていた生き物の画像のファイル名にして(NTG_01など)、説明文も一切省きました。「生き物の名前がファイル名」というアイデアは、主人公がロボットだったため、「ロボット目線」というこじつけの理由を考えてとりあえず自分を納得させることにしました。それをユーザーには伝えていないので、たぶんそこは批判されるだろうと思ってリリースしましたが、実際はユーザーは「元ネタはなんだろう」と想像を巡らせて推理を楽しんでくれたんです。

――お二人ともゲーム開発をしながら配信活動もされていますね。
ウマー 配信はプロモーションや応援してくれる方々との交流のための活動で大事なのですが、私は制作と配信活動の主従関係をはっきり決めていて、制作はメインで配信活動はサブとしています。なので配信スケジュールを決めてやるといったやり方の方がプロモーション的な観点でいうと正解だとは思いますが、制作が優先なので配信は不定期配信にしています。
マイペースにやっているのでそんなに成果を期待もしていませんでしたが、予想していたよりもたくさんの方に見に来ていただけるようになりましたし、私の精神的な一つの居場所として、いい息抜きの場になりましたね。
小林 ツイキャスの作業配信についてはウマーさんと同じスタンスです。つくるついでに配信もしていて基本はランダムです。これは個人開発だからできることですね。
ウマー 小規模ゲーム開発における制作配信は、結構リスクを感じる人は多いんじゃないかなと思います。ネタバレを公開することでリリース時の売上に響くんじゃないかとか、いろいろ理由はあると思います。
ネタバレについては持論があって、例えばそのゲームのネタをすべて一人のファンの人が配信で知ったとして、そのくらい配信に来てくれる人は絶対にファンだと思うので、買ってくれる可能性は高い。すべてを知った上で、配信で見た内容を振り返りながら巡るという独自の遊び方ができますし、それでも知らなかった発見を見つける楽しみもある。それは熱心なファンならではの贅沢な遊び方なんじゃないかなとも思います。初期のネタがリリース時にそのまま残っていることもあまりない気もしますし、結局のところ、ネタバレは気にしなくてもよいのではないかというのが僕の考えです。
制作者自身やゲームのファンになってくれて、日頃からSNSのリアクションで拡散に協力してくれたり、モチベーションや精神的な支えになってくれたり、配信活動をすることによるデメリットよりも、メリットの方が大きい気はしています。
小林 制作過程もエンタメになるんですよね。個人開発ではできますが企業だとコンプライアンスもあるので難しいでしょう。配信内容は絵になりますね。コーディングとかだと考えながらやっていて話せないですよね。
ウマー それは同じですね。でも、コーディング配信もやってみたらエンジニアの人が喜んでくれたりしたことがありました。
――ゲームの個人開発ならではという話がありましたが、フリーランスとしての受託業務、会社でのお勤めもあるなかで、仕事と個人開発のバランスについてはどのようにされていますか。
ウマー 仕事と個人開発のバランスは、年齢や状況によって変化させてきていますね。フリーランスになりたての頃は、生活を安定させるためにほとんどの時間を受託業務に当てて個人開発は合間にちょっとやる程度。貯蓄もある程度安定して生活に余裕が出てきたら、受託の数を抑えて個人開発と半々くらいのバランスで進めるように変えてきました。
そこから先は年齢を考えますね。やはり歳を取るにつれて体力も落ちて生産性が下がってくると思うんです。だから受託業務に生活を依存したままだと危険なので、自分のコンテンツや独自のファンをつくって応援してもらえるような体制づくりに徐々に注力して、土台をつくっておく。最終的にはたまにおもしろそうな受託仕事ができて、基本的にはすべてオリジナルコンテンツで生活ができる、というような体制にたどり着けたらいいなと思っています。
小林 私は仕事は仕事、プライベートはプライベートと思っていて。理由は自分が好き勝手つくっているゲームを生活のためにつくり出すと、妥協したり早く出そうとしたりしてしまうんじゃないかと思っているからです。仕事ではきっちり会社に貢献して、プライベートはコスト度外視で好きにやろうというスタンスです。なので、これが一緒になるとバランスが崩れるんじゃないかと。締め切りを設けてしまうと私の生活に合わない気がします。あとは、仕事で学んだことやプライベートで得たことがお互いに役に立っていたりして、これも悪くないなと思うこともあります。年齢的に明らかに体力も落ちていて、電車の中でタスクを片付けるとか工夫もしています。
ウマー 私も『Remain On Earth』に関しては資金とプロジェクトを完全に切り離しています。でも『Fishing The Abyss』を一定評価していただいたのを経て、「商業商品としての小規模ゲーム」もアリなんじゃないかと思っています。好きにつくることが楽しいゲームづくりだと思っていましたが、ちゃんとお金を稼ぐためにつくるゲームも、全然違う楽しさがあることに気付きましたね。
――お二人の作品についてですが、ウマーさんであれば『Fishing The Abyss』の解説に「忙しくてゲームがプレイできない人向け」と書かれています。ご自身のゲームのターゲット層やどういうコンセプトにするかの点はどのように決めていますか。
ウマー ターゲットは私自身の心境をそのまま反映させました。
ゲーム開発をしているとゲームを遊べなくなるんですよね。実は遊ぶのもつくるのもどっちも同じくらい楽しいんですが、違うポイントがあるんです。ゲームを遊ぶと、キャラクターが経験値を得てレベルアップして、敵を倒してお金を稼ぎますよね。でもこれはあくまでゲームのなかの話です。ゲーム開発は、私自身に経験値が入って、私自身のスキルがレベルアップして、結果ちゃんと現実のお金が稼げるんですよ。なので遊ぶ選択が取りづらいんです。そういった心境があるので、まさに自分の悩みをターゲットにできたというところですね。
もう一つ理由があります。「忙しくてゲームがプレイできない人向け」と聞くと直感的に放置ゲーム1が連想しやすいと思うのですが、放置ゲームにすることでプレイヤーに選択肢をあまり与えなくても成立するゲームサイクルがつくれると思ったんです。選択肢が少ないことは、その分バグも少なくなる可能性が高いわけで、開発側がコントロールできる領域を広く持てる分、コスト面で有利と考えました。
――小林さんであればオープンワールドの作品をつくっているなかで、15分タイムアタック体験版を公開されていましたが、これはどういった考えだったのでしょう。
小林 オープンワールドは完成まで遠いので、ウマーさんと別のアプローチとして、どこかで区切りをつけようと思っていました。オープンワールドの体験版は本来つくりづらいんですね。自由度が高いので土地を区切って遊べるようにしても、そのなかで無限に遊べるんです。それで体験版との相性が悪いなと悩みながらイベントに出たんですが、ずっと遊ぶ人がいて他の人が遊べないことがあったので、5分くらいの時間制限を入れたんです。それでスコアとかを競う要素を加えたら楽しいんじゃないかと、導入してみたら評判が良くてこれを本編にいれてほしいという声もあったりして、逆輸入しようと思っています。これは偶然の産物なのですが、インディーゲーム開発って偶然の産物を上手く活用するのがカギになりますね。制限とか縛りを生かすのが本当に大事だと、15分体験版導入のときに感じました。
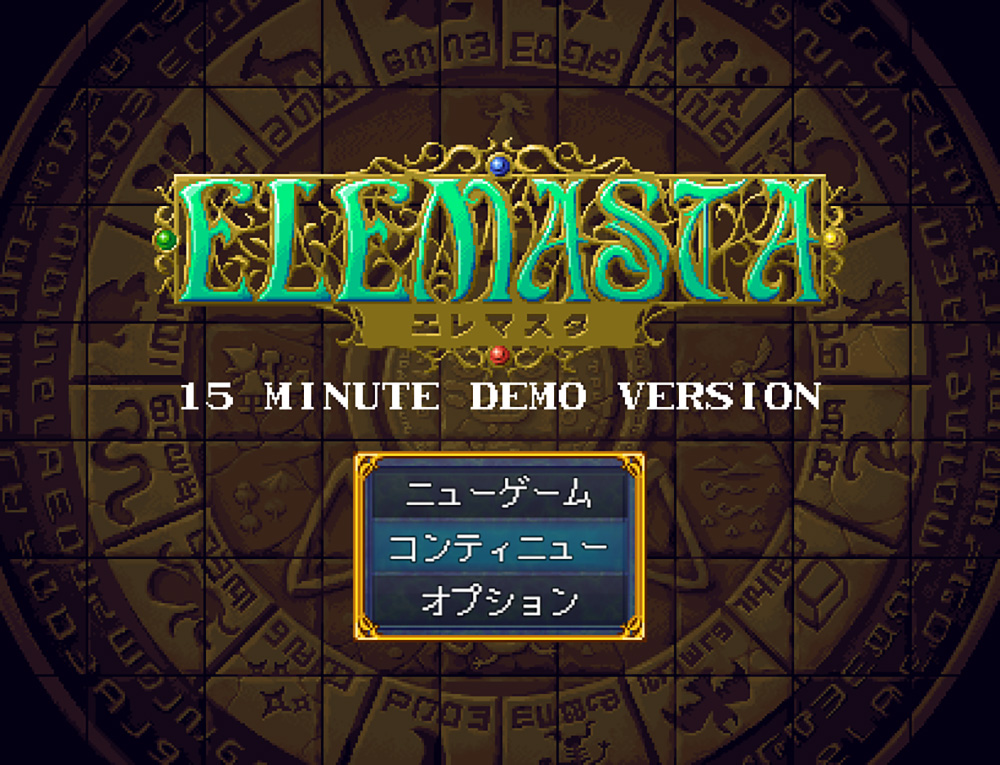
――海外の反応はいかがでしょうか。
ウマー もともと海外はあんまり視野に入れていませんでした。ゲームタイトルを最初から英語にしたり、設定資料集などの自作の本には必ず英語翻訳文も載せていたり、できる範囲で意識はしていましたが、ゲーム自体に海外での販売は考えていなかったんです。
でも『Fishing The Abyss』は大したテキストの量じゃないなと思ったので、経験として多言語対応やってみるかということで気軽な気持ちで実装してみたんですよね。そして実際にリリースしてみたら、売上の半分以上が海外だったんです。なので今後は絶対視野に入れていきたいです。
小林 ウマーさんと同じく、テキストが多いのでどうだろうと思っていたんですが、体験版は短いからやってみようと試してみると反応は良かったんですね。翻訳の経験がある人にいろいろ聞いてみると、シリアスなRPGは翻訳が微妙だと評価に直結するんですが、僕の作品を英語のできる友人にも見てもらって、これなら大丈夫じゃないかという判断になりました。体験版でデーターベースの翻訳はできたので、英語はやってみようと思います。データーベースも英語に対応するために簡素化したりしています。中国語対応はまだ考えていないですが、フォロワーのうち海外の人が3割くらいなので、JRPGは最近海外の人がプレイすることが多いこともあり、積極的にやっていこうと思っています。
――話題は尽きませんが、最後にこの記事をご覧の皆さんに一言お願いします。
ウマー いろいろと偉そうに語りましたが、インディーゲームと一括りにしてみても、なかには個人的な楽しみとしてゲームをつくっていきたい人や、商業的に成功したい人など、ゲームをつくっている人の目的も多種多様で、そういう人たちが誰かに向けて何かを伝える目的も、多種多様です。
なので私はこういう風に誰かに向けて何かを伝えるときはとても言葉を選びます。商業を目指す人向けのコメントが、趣味でやっている人に違う形で刺さって精神的にダメージを負わせたりすることがよくあるからです。この記事がどういう立場で誰に向けられているのかを考えて、自分に向いていなければ無視したっていいと思っています。
小林 ウマーさんの話にかぶるんですが、インディーゲームはゴールがいろいろあります。表現がしたいのか、成果を出したいのか、つくったという実感がほしいのかなどで、作品の方向性やつくり方が変わって来ることがおもしろいと思っています。ガチ目につくっている視点からいうと、つくると同時にプロモーションをしていく必要性があるわけですが、プロモーションって楽しいものなんじゃないかと。「完成しました!」「リリースしました!」「終わり!」と告知するだけでなく、やり方によっては、開発による成果物や表現や考えについて、交流が生まれたりするんです。受注して開発するのとは違って、プロモーションの広げ方も自分の趣味嗜好に合わせられます。プロモーションしないといけないと考えるより、いろいろ楽しんだ方がいい気がします。お金が儲かるのだって楽しいかもしれないし、自由にできる環境なんだから、自分を苦しめずに楽しんでやれる方法を模索したらいいんじゃないかなと思っています。
――ありがとうございました。
脚注
ウマー
個人開発のゲームクリエイター。代表作は自動で深海釣りを楽しむデスクトップアプリ『Fishing The Abyss』(2024年)、制作中のドット絵アドベンチャーゲーム『Remain On Earth』。ドット絵を中心に、音楽と効果音以外の部分を個人で制作している。
小林 光
デザイナー。ゲーム業界に約30年在籍、PlayStation、セガサターン、ドリームキャストを経て、ガラケーアプリやスマホのソーシャルゲームなど、累計150作品ほどに携わる。ドット絵から3D、時にメインプランナーやディレクターも経験し、今は社会人のかたわらで個人でもゲーム制作を行う。
※インタビュー日:2025年6月26日
※URLは2025年11月18日にリンクを確認済み