野村 崇明
2023年11月に、北海道の新千歳空港ターミナルビルにて開催された第10回新千歳空港国際アニメーション映画祭。2014年の初開催以来、この映画祭は独自の試みを行い続けてきました。本稿では、10回目の節目を迎えるこの映画祭が何を行い、どう変化してきたのかを、ほかのアニメーション映画祭との比較を交えつつふりかえります。さらに、今回の映画祭で受賞した作品を取り上げ、昨今の映像的な文脈、社会情勢、新しい技術から生まれる表現についても考察していきます。

2023年11月2日(木)から6日(月)にわたって、第10回新千歳空港国際アニメーション映画祭(以下「新千歳」)は行われた。新千歳空港のなかで行われるこの映画祭は、2023年で第10回の節目を迎え、開催期間もそれまでの4日間から5日間に拡張された。

一般的に国際アニメーション映画祭は、ディズニーや日本のテレビアニメといった産業アニメーションとは作風の異なる、個人作家による作家独自の表現(それはしばしば、「インディペンデント・アニメーション」や「アート・アニメーション」と呼ばれる)にフォーカスを当てることを特徴としている。例えば日本においては、世界四大アニメーション映画祭の一つとして数え上げられていた広島国際アニメーションフェスティバル(1985〜2020年まで基本的に隔年で開催、第2回から第3回のみ3年間隔での開催)が、そういった役割を担ってきた。そこでは、コマ撮りのつくり出す作家独自の動きのリズムや、手書きによるオリジナリティのある画風が高く評価されてきた。
一方で新千歳が設立された2010年代というのは、このような伝統的な映画祭の評価基準が二つの方向で大きく揺らいだ年であった。まず一つ目は、CGの隆盛によって、コマ撮りや手書きが必ずしもアニメーションの主要な制作方法とは言えなくなり、動きや画風の独自性という評価基準が絶対的なものではなくなったこと。二つ目は、産業アニメーションとインディペンデント・アニメーションの境目が、自明なものではなくなってきたこと。広島国際アニメーションフェスティバルが伝統に根ざしたインディペンデント・アニメーションの持つ高い芸術性を伝え続ける一方で、新興の映画祭である新千歳は、設立時から現在に至るまでこういったアニメーション環境の変化に着目し、アニメーションに対する新しい評価基準をつくり出すことを自らの役割とし続けてきた。
例えば2014年に開催された第1回においては、特別レクチャーの講師としてデビッド・オライリーを招聘している。『おねがい なにかいって』(2008年)や『エクスターナル・ワールド』(2010年)を代表作に持つオライリーは、ポリゴンやグリッチといった不完全な3DCGを積極的に活用するアーティストだ。彼は自らの用いる3DCGの特徴についてしばしば「野生」という言葉を用いており、誰でも同じように使えるがゆえのオリジナリティの希薄さを強調している。アドバイサーやフェスティバル・ディレクターという形で、第1回から第8回まで本映画祭に深く関わり続けてきた土居伸彰は『21世紀のアニメーションがわかる本』(フィルムアート社、2017年)において、こういった3DCGの「野生」性が、観客の自由な解釈を誘発し、画面の上に描かれているものにさまざまな意味を宿らせると述べている1。つまりオライリーのアニメーションは作家独自の視点や内的世界を表現したものではなく、さまざまな観客がさまざまに解釈や意味を与えることで、限りない広がりを持ち続けるのだ。新千歳は初回から現在に至るまで、伝統的な映画祭の評価基準に必ずしも即しているとは限らない、オライリーのような独自の美学を持つ作家をフックアップし続けてきた。
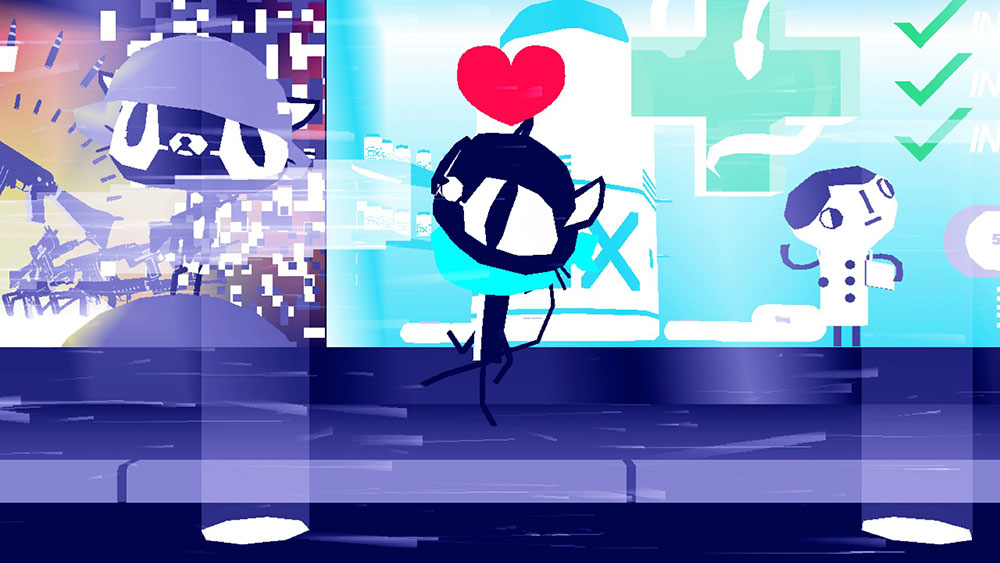
また2018年に開催された第5回からは、それまで短編部門のみであったコンペティションに、新しく長編部門が追加された。すでにほかの映画祭でも多数の賞を受賞していた『This Magnificent Cake!』(2018年)から、日本の産業アニメーションである『少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR YOU- 完全版』(2018年)まで幅広い作品がノミネートされており、産業/インディペンデントという括りに捉われない評価軸を模索していたことがうかがえる。また同年の映画祭のメインビジュアルは、卒業制作『Airy me』(2013年)からテレビアニメ『宝石の国』(2017年)のED映像まで、個人と産業の境を飛び越えながら仕事を続けてきた久野遥子が制作しており、会期中には久野によるレクチャープログラムも開催された。
このように新千歳は映画祭シーンにおいて独自の役割を担い続けてきた。一方で2022年から2023年にかけて、日本の映画祭シーンでもこういった新千歳の試みと共鳴するような、二つの大きな変化が起こった。
まず一つ目の変化は、2020年に終了した広島国際アニメーションフェスティバルの後継として、2022年にひろしまアニメーションシーズンが新設されたことだ。新千歳とひろしまアニメーションシーズンはコンペティションの分け方や審査員のライナップなどに大きな違いがあるが、伝統的な映画祭とは異なる、新しいアニメーションの評価基準を立ち上げようとする方向性自体は、二つの映画祭のあいだで共有されている。また、それまで日本では新千歳でしか見ることのできなかった作品の多くが、ひろしまアニメーションシーズンの新設により広島でも見られるようになった。
二つ目の変化は、2023年に新潟国際アニメーション映画祭が新設されたことだ。この映画祭は新千歳やひろしまアニメーションシーズンとは違い、短編ではなく長編を中心とした映画祭であるが、コンペティションにはインディペンデント・アニメーション作家、ロストによる『四つの悪夢』(2020年)から日本のアニメ制作会社WIT STUDIOによる『劇場版 ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン』(2022年)まで、産業とインディペンデントの垣根を超えた幅広い作品がノミネートされている。
二つのアニメーション映画祭の新設は、新千歳の目指してきた方向性が、ここ数年で新しいスタンダードの一つとなってきていることを感じさせる。それは同時に、これまで新千歳の独自性であったものが、必ずしも新千歳の専売特許ではなくなっていることをも意味するだろう。では第10回という節目を迎えた新千歳は、このような変化のなかで、どのような独自性を打ち出したのか。
映画祭のチーフディレクターである小野朋子は、映画祭の開催に寄せたメッセージのなかで、「アニメーションの意義を拡張させる遊び場」という言葉を用いている。この理念の体現として、第10回の新千歳では「作品」としてパッケージされたアニメーションのみならず、日常にあふれる広義のアニメーションやアニメーション技術にもフォーカスが当てられていた。
例えばSNSに投稿されたGIFや数秒のショートアニメのコンペティションとしてNEW CHITOSE AIRPORT Social Media Animation Awardが開かれ、大賞受賞者はほかのコンペティション受賞者と同じく映画祭へと招待された。また「NEW CHITOSE ARport Walk」と題されたプログラムでは、新千歳空港内4カ所でARを用いたアニメーションが展示され、さらに新千歳空港内で行われた「STREET WRITER」というプログラムでは、クリエイティブユニットTOCHKAの製作したARアプリケーションを用いて空間に落書きをし、それをほかの利用者と共有するという試みが行われた。ここで注目したいのが、こういった広義のアニメーションや技術を紹介するプログラムにも、コンペティション部門の選考メンバーが関わっているという点だ。

例えばNEW CHITOSE ARport Walkは、映画祭のアドバイサーでありコンペティション部門の選考メンバーも務めているTOCHKAが総合ディレクターを担っており、また同じく選考メンバーである岩崎宏俊もNEW CHITOSE AIRPORT Social Media Animation Awardの審査員を務めている。国際アニメーション映画祭の花形はコンペティションであり、どのような作品をノミネートさせるかが映画祭の色を決めるといっても過言ではないが、新千歳の場合、コンペティションとそれ以外のプログラムの間にも、共通した問題意識があるのだ。
しばしば言われるように、現代の映像文化においてアニメーション作品を定義することは難しい。実写映画であってもCGやVFXが当たり前のように使われているし、アニメーション作品の側でもしばしばロトスコープやモーションキャプチャといった、実写映像の動きをトレースする技術が用いられている。またTikTokやSNOWといったアプリにおいても、自分自身を映した映像にアニメーションエフェクトをかけることは頻繁に行われており、むしろ何の加工も施されていない実写映像を不自然だと感じることも多い。新千歳のプログラムは、実写とアニメーションの境が曖昧になっている映像環境の変化を捉えたうえで、「アニメーション映画」の範囲を作品としてパッケージされ流通しているものに留めず、アニメーション技術を用いた試み一般にまで拡張しているように思える。
こういった拡張は、ありとあらゆる映像を「アニメーション映画」の範疇に収めるために行われるのではない。むしろ短編・長編コンペティションに応募されてくる作品の側こそが、こういったアニメーションをめぐる環境の変化に敏感に反応しており、そういった作品を正しく評価するためにこそ「アニメーション映画」の範囲を広げる必要がある。
例えば日本コンペティションにノミネートされ、北海道知事賞を受賞した大島慶太郎『マイスクール』(2023年)。この作品は大島が撮影した実写映像をピクシレーションのようにコマ送りした映像に、舞台である札幌市立藤野南小学校の生徒たちが描いた絵を組み合わせた作品となっている。アーティストと地域の人々の交流を目的としたアートプロジェクト、AIS(Artist In School)の一環としてつくられたこの作品には、地域の小学生を対象としたアニメーション・ワークショップとしての側面も多分に含まれているのだが、ここで着目したいのは、このワークショップにおいて用いられている技術がロトスコープ(実写映像のトレース)であるという点である。アニメーション制作における小学生たちの役割は実写の映像から抜き取られた一コマをなぞってドローイングに変えることであり、そこではコマ撮りによるドローイング・アニメーションと、フィルムを用いた実写映像とが、コマという共通の原理によって動いていることが強調されている。

もちろん実写とアニメーションを通底させる試み自体は、実験映像の分野において数多く見受けられる。『マイスクール』が特異なのは、こういった試みを前衛的な実験としてではなく、ワークショップとして行っているところだ。子どもたちにとって、アニメーションのために絵を描くというのは、かなりハードルの高い課題であろう。しかし実写映像から切り取られた一コマを、自分の好きな色や画材を使ってなぞるだけならば、いくらか簡単にできる。『マイスクール』における実写とアニメーションの混交は、実験や前衛ではなく、むしろアニメーションをより身近なものにしているのだ。
「アニメーション」という言葉は、もはや作品のジャンルを示す言葉としては充分に機能しえない。アニメーション映画と実写映画を厳密に区別することはできないうえ、私たちは日々アニメーションとも実写ともいえない映像を違和感なく享受しているからだ。『マイスクール』はこういった状況を、アニメーション映画の困難としてではなく、アニメーションを万人に開くためのチャンスと捉えているように見える。現に、『マイスクール』に現れる子どもたちの絵は、どれも大変個性的だ。子どもであろうと大人であろうと、自由に描いた絵というのは画一的になりがちであるし、ましてや最終的に動かすとなれば、各々が個性を出すのは難しい。しかしロトスコープを用いれば、それぞれの子どもたちがどう好き勝手になぞろうと(あるいはほとんどの線をなぞるのを放棄しようと)、アニメーションとして成立する。かつてはアニメーション作品に個性を宿らせるためにどういった絵を描き、どういった動きをつくるべきなのかが問題であったが、ここではむしろ、ロトスコープというアニメーション技術を通して、子どもたちがどういった個性を発揮すべきなのかが問題となっている。
新千歳がアニメーション映画祭でありながら、広義のアニメーション技術を用いた試みまでをも取り扱うのは、狭義のアニメーション作品の側にこういった変化が見られるからだ。第10回新千歳長編部門グランプリを獲得したキアラ・マルタ、セバスチャン・ローデンバック『リンダはチキンがたべたい!』(2023年)も、アニメーションを用いて何を行うのかを問題としている。
この作品は、世界最大のアニメーション映画祭であるアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門でクリスタル(グランプリ)を獲得し、2024年には日本国内での配給も決まっている注目作だ。

あらすじとしては以下のとおり。主人公であるリンダは、母親であるポレットに、チキン煮込みをつくってもらう約束を取り付ける。しかし、その日は労働者ストの日であったため、どこに行ってもチキンを手に入れることができない。娘との約束を守るためにポレットは、リンダとともに町中を駆け回り、大騒動を起こしていく。
無理やりあらすじとしてまとめてみたものの、実際にこの作品を見てみればわかるとおり、この作品のストーリーは奇想天外な出来事の連続で、次に何が起こるのか想像もつかないような奔放さを持っている。
ここで思い起こしておきたいのは、監督の一人であるセバスチャン・ローデンバックの前作『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』(2016年)である。ローデンバックはこの作品で用いた手法を「クリプトキノグラフィ」と名付けている。この作品の登場人物は、どれも必要最低限の書き込みしかなされておらず、一枚絵からそのパーソナリティを読み取ることが難しい。しかし観客は、登場人物たちが動いている姿を見ることで、描かれているのが何者なのかを理解することができる。ローデンバックは観客に読み取りを要求するこういった手法を、暗号になぞらえて「クリプトキノグラフィ」と呼んでいる。
一方『リンダはチキンがたべたい!』においては、主要な登場人物たちにパーソナルカラーが設定されており、前作と比して登場人物ごとのパーソナリティが掴みやすいように見える。しかしこのパーソナルカラーが、多くの場面において輪郭線を飛び出ていることを見逃してはならない。例えばポスタービジュアルにおいては、登場人物たちはみな輪郭線に合わせてパーソナルカラーを着色されている。しかし作品のなかに現れる、活発に動き続ける登場人物たちは、自らを押し込める輪郭線や立場といった縛りを飛び出していくかのように、多くの場面においてパーソナルカラーをあふれださせている。そして彼らは、行動やパーソナリティを予測する観客たちの読みを超えていく。
そもそもアニメーションというメディア自体、常に観客による読みを必要としている。いうまでもなく、アニメーション作品に現れるりんごは単なる絵であり、現実のりんごを直接映したものではない。観客がその絵をりんごだと読み取ることができたとき、初めて絵は現実のりんごを模した記号になる。そして観客がアニメーションを読むためには、例えば「へのへのもへじ=人間の顔」といった、読解のルールを身につける必要がある。『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』における「クリプトキノグラフィ」は、さながら暗号を解読するときのように、観客に読解のためのルールを探らせ、新しいルールを身につけさせる試みだったといえるだろう。
それに対して『リンダはチキンがたべたい!』が行うのは、ルールのハッキングである。例えばリンダの行動のみに焦点を当てれば、彼女がチキンを食べるためにニワトリを追いかけ回しているのだと読み取れるし、展開を予想することも充分に可能である。しかしこの作品が奇想天外に見えるのは、数多くの登場人物たちの思惑が複雑に絡み合った結果、登場人物の立場や行動の意味が常に移り変わり続けるからだ。リンダは時に何かを追いかけ、時に誰かに追いかけられる。また彼女は時に加害者に、時に被害者になる。「リンダはこういう人物だ」という読みや、「このあとリンダはこうするだろう」といった予測が裏切られ続けるのは、登場人物たちを理解するために必要な読解のルールが、別のルールの介入によって、めまぐるしく変化し続けるからなのだ。
アニメーションは読まれることによって現実を描く。『リンダはチキンがたべたい!』はこの読みのルールを変化させる。そしてこの作品の白眉は、こういったルールを変える力を、現実の政治的出来事に対して行使している点にある。
そもそもストライキのせいでチキンが買えないという設定自体、パリで2022年以来ストライキが多発しているという事実を背景としている。またこの作品の後半部には、1968年の五月革命を思わせる描写が数多く存在する。こういった政治的な描写はまた、その多くがパロディされ、滑稽なものとして描かれている。
例えば人々の集まる広場を煙が覆うシーンは、五月革命の際、暴徒鎮圧のために用いられた催涙ガスをイメージさせる。しかし、この作品において煙の正体は焦げた野菜である。また子どもがスイカを投げる際には、機動隊の発砲音を思わせるSEが流される。こういったパロディは、五月革命時のフランス大統領ド゠ゴールの有名な言葉、「(パリでの暴動は)子どもの遊びさ」を文字どおり実践している。そしてこの「子どもの遊び」は、厳密なルールを持たない。すでに知っている遊びのルールから、別のルールに切り替わる可能性を常に持っている。
描かれた政治的出来事の結末を、観客たちの多くは知っている。その評価は人によってさまざまであるが、問題なのはこういった出来事についての記憶が、少なくない人々にとって政治的無力感と結びついてしまっているという点だ。『リンダはチキンがたべたい!』はこういった出来事をパロディし、一度観客たちに読み取らせたうえで、予想外の展開を用意し、読みのルールを裏切っていく。現実の出来事から読み取られるさまざまな負の感情や、そこから導き出される帰結をも、アニメーションを用いて読み替えてしまうのだ。
『リンダはチキンをたべたい!』をスクリーンで見たときに私が思い出したのは、AR技術を用いたゲームであった。例えば『Pokémon GO』(2016年)では、現実世界の地理がほぼそのままアプリ内に表示され、マップとして扱われる。このマップはデータを基にしたつくり物でしかないが、あたかも現実世界のミニチュアであるかのように感じられる。そしてマップ上にポケモンたちが現れるとき、私は現実世界と似たルールを持つミニチュアに、まったく別のルールが介在してきたような感覚を覚えた。アニメーション技術も作品も、現実それ自体を変えはしない。しかし、『Pokémon GO』や『リンダはチキンをたべたい!』は、私たちが生きる現実のルールが可変的であり、私たちの予想を裏切るような出来事が起こりうるという可能性を示してくれる。
短編部門グランプリに輝いたジョシュ・シャフナー『In Dreams』(2023年)が描き出すのも、こういった可変的なリアリティであるように思われる。火傷を負った男がホスピスで見る夢を描いたこの作品は、内容やアートスタイルも含め、スーザン・ピットの影響を強く受けている(ジョシュ・シャフナー自身、スーザン・ピットのアシスタントを務めたことがある)。また、自らの無意識を印象的なスタイルで表現しているという点において、ブルース・ビックフォードの系譜に位置付けることもできるだろう。しかしこの作品が特異なのは、無意識や夢を自分だけのリアリティとして描くのではなく、現実が変換されたものとして描いているという点だ。

この作品のいくつかの描写は、量子力学(原子や分子、素粒子といった極めて小さい物体を扱う物理学)の影響を感じさせる。量子力学があつかう極小の物質は、私たちが生きる通常の世界における物理学とは全く違ったルールを持っており、その最たるものは、運動が一方向に限定されないというものだ。私たちは分かれ道に差し掛かった時、右か左のどちらかの道を選ぶが、極小の物質は、右にも左にも同時に行く。つまり量子力学においては、物質が右に行った世界と左に行った世界の、両方が同時に存在しうる。ここから、マルチバースや並行世界といった仮説も導かれてくる。
もちろん量子力学における平行世界とは実際に存在するものではない。あくまで、この世界の法則を描くために、どうしても平行世界における別の法則を前提としなければならないという話でしかない。ただこれは裏を返せば、私たちの生きるこの世界の法則が、常に別の法則の存在を必要としているということであり、それらはお互いを参照し合っているがゆえに、お互いがお互いの姿に変換されてしまう可能性を含んでいるということでもある。
『In Dreams』において、主人公の男が夢の世界に旅立つためには、彼の暮らす病室が歪み、別の世界へと変換されるという前置きが必要であった。夢や無意識の世界を描く作品の多くは、そういった世界を自分だけの秘密の空間として扱うか、現実よりもリアルな超現実として扱ってきた。しかし『In Dreams』において夢の世界は、現実とお互いを参照し合う平行世界のような扱いをされている。だからこそラストシーンにおいては、二つの世界が混ざり合うことができるし、それが驚愕のラストを導き出すこととなる。
第10回を迎えた新千歳が示したのは、ジャンルとしてのアニメーション映画がその輪郭を失った後に現れてくる、「アニメーション技術を用いて、何を行うのか」という問題であった。そしてコンペティションのグランプリ作品から見えてきたのは、アニメーションを用いることで、この世界は読み替え可能なものとなるという可変的なリアリティであったように思われる。
脚注
information
第10回 新千歳空港国際アニメーション映画祭
会期:2023年11月2日(木)~6日(月)
会場:新千歳空港ターミナルビル(新千歳空港シアターほか)
料金:座席指定券1,000~3,000円、3プログラム回数券2,700円(前売り)/3,000円(当日)、5プログラム回数券4,000円(前売り)/4,500円(当日)、当日券1500円~3500円
https://airport-anifes.jp/
※URLは2024年3月5日にリンクを確認済み